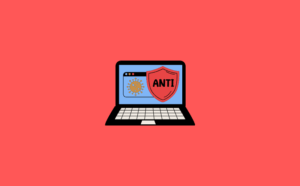中小企業の経営者必見!社内パスワード共有の正しい方法と「定期変更は逆効果」の真実

「社員みんなで同じパスワードを使っているけど、これって危険なの?」、「毎月パスワードを変更するよう指示しているのに、なぜかトラブルが減らない…」
中小企業の経営者から、このような相談を受けることが増えています。実際に、多くの会社で以下のような「危険な状況」が常態化しています。
- 重要なシステムのパスワードを付箋に書いてパソコンに貼っている
- 全社員が同じパスワードを使い回している
- 「セキュリティのため」と称して毎月パスワード変更を強制している
- 退職した社員が使っていたパスワードがそのまま残っている
- 緊急時にパスワードがわからず業務が止まってしまう
この記事では、 中小企業の経営者が知っておくべきパスワード管理の「新常識」を、ITの専門知識がなくても理解できるよう解説します。特に、「パスワード定期変更は逆効果」という最新の考え方についても詳しくお伝えします。
なぜ今、パスワード管理の見直しが必要なのか?
警察庁の発表によると、令和5年(2023年)中の不正アクセス禁止法違反による検挙は521件・259人で、そのうち487件(約94%)が他人のIDやパスワードを無断で入力する「識別符号窃用型」の不正アクセスでした。多くの場合、 パスワード管理の甘さが原因となっています。
中小企業が狙われやすい3つの理由
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の2024年度調査では、中小企業がサイバー攻撃の標的になりやすい理由として以下が挙げられています。
- セキュリティ対策の専任担当者がいない
- 限られた予算でIT投資を行う必要がある
- 従業員のITリテラシーにばらつきがある
つまり、中小企業こそ、基本的なパスワード管理を確実に実施することが重要なのです。
テレワーク普及でリスクが急増
総務省の令和4年度調査によると、テレワーク実施企業の52.0%が「セキュリティの確保」を課題として挙げています。自宅や外出先からの業務が増えることで、パスワード管理の重要性はさらに高まっています。
実際に、以下のような事例が報告されています。
- カフェの無料Wi-Fiでログインしたところ、パスワードが盗み見された
- 家族共用のパソコンから業務データが流出した
- 簡単なパスワードが推測され、顧客情報が漏えいした
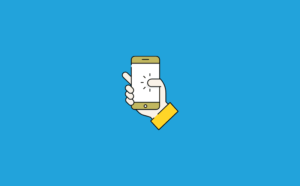
「パスワード定期変更は無意味」は本当なのか?最新の考え方を解説
長年「常識」とされてきた「パスワードの定期変更」ですが、実は2017年以降、世界的に考え方が大きく変わっています。
総務省とNISTが方針転換した理由
2017年6月、米国国立標準技術研究所(NIST)が発表したガイドライン「SP800-63B」で、「サービス提供者はパスワードの定期変更を要求すべきでない」という方針が示されました。さらに2024年8月の最新ドラフトでは「定期変更を要求してはならない」とより強い表現に変更されています。これらを受けて、2018年3月に総務省も「パスワードの定期的な変更は不要」と発表しています。
なぜこのような方針転換が起きたのでしょうか?理由は以下の通りです。
定期変更が引き起こす4つの問題
- パスワードの単純化:覚えやすさを優先し、「password1」「password2」のような推測しやすいパターンになる
- 使い回しの増加:複数のサービスで同じパスワードを使ってしまう
- メモの増加:覚えられずに付箋や手帳に書いてしまう
- 管理コストの増大:変更作業やパスワードリセット対応に時間がかかる
「定期変更不要」の正しい理解
ただし、「定期変更不要」には重要な条件があります。
- 十分に強力で推測されにくいパスワードを使用している
- サービス間でパスワードを使い回していない
- パスワード流出や不正アクセスの兆候がない
つまり、 「良いパスワードなら変更しなくてよい」が正しい理解です。逆に、以下の場合は即座にパスワード変更が必要です。
- パスワードが流出した可能性がある
- 不正アクセスの形跡がある
- システムがサイバー攻撃を受けた
- 関係者の退職や人事異動があった

中小企業で起きがちな「危険なパスワード社内共有」とは?
パスワードの社内共有は、業務効率化のために必要な場面もありますが、適切に行わないと大きなリスクとなります。
よくある危険な共有方法
以下のような方法でパスワードを共有していませんか?
- メールやチャットで送信:平文でのやり取りは第三者に見られるリスクが高い
- Excelファイルで管理:ファイル自体が流出すると全てのパスワードが漏れる
- 口頭や付箋で伝達:聞き間違いや紛失のリスクがある
- 簡単なパスワードに統一:「password123」のような推測しやすいものを全社で使用
パスワード共有で起きる4つのリスク
不適切なパスワード共有は、以下のようなリスクを生み出します。
1. 情報漏えいリスクの拡大
一人のパスワードが漏れただけで、複数のシステムに不正アクセスされる可能性があります。実際に、共有パスワードが原因で顧客情報が流出し、損害賠償請求を受けた中小企業の事例も報告されています。
2. 責任の所在が不明確
同じパスワードを複数人が使用していると、問題が発生した際に「誰が何をしたか」を特定できません。これは、内部統制の観点からも大きな問題です。
3. パスワード強度の低下
共有しやすいよう、覚えやすく簡単なパスワードを設定する傾向があります。これにより、パスワードが破られやすくなります。
4. 管理の複雑化
人事異動や退職の際に、どのパスワードを変更すべきかわからず、セキュリティホールが生まれる可能性があります。
安全なパスワード共有を実現する5つの方法
それでは、中小企業が実践できる安全なパスワード共有方法をご紹介します。
方法1パスワード管理ツールの活用
最も効果的な解決策は、専用のパスワード管理ツールを導入することです。
パスワード管理ツールの主な機能
- 強力なパスワードの自動生成
- 暗号化された安全な保存
- 必要な人だけにアクセス権限を付与
- ログイン履歴の確認
- 緊急時の一括変更
中小企業向けのパスワード管理ツールは、月額数百円から利用できるものもあり、 セキュリティ強化とコスト削減を両立できます。
方法2役割ベースのアクセス制御
全員が全てのパスワードにアクセスできる状態は危険です。以下のように役割を分けて管理しましょう。
- 管理者:全パスワードの閲覧・編集・削除権限
- 部門責任者:担当部門のパスワードのみ閲覧・編集権限
- 一般社員:必要最小限のパスワードのみ閲覧権限
方法3共有パスワードの定期監査
以下の点を定期的(四半期に1回程度)にチェックしましょう。
- 不要になったアカウントの削除
- 退職者が使用していたパスワードの変更
- アクセス権限の見直し
- パスワード強度の確認
方法4緊急時対応手順の策定
パスワード流出が疑われる場合の対応手順を事前に決めておきましょう。
- 該当アカウントの即座停止
- 被害範囲の調査
- 関係者への報告
- パスワードの変更
- 再発防止策の実施
方法5社員教育の実施
技術的な対策だけでなく、社員一人ひとりの意識向上も重要です。以下の内容を含む研修を定期的に実施しましょう。
- なぜパスワード管理が重要なのか
- 安全なパスワードの作り方
- フィッシング詐欺の見分け方
- インシデント発生時の報告方法
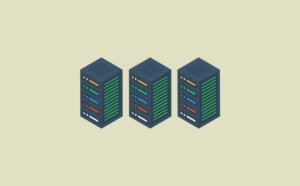
強力なパスワードを作るための実践的なコツ
「定期変更不要」の条件である「強力なパスワード」を作るためのコツをご紹介します。
推奨されるパスワードの条件
IPAの推奨する安全なパスワードの条件は以下の通りです。
- 最低でも10文字以上(理想は12文字以上)
- 大文字・小文字・数字・記号を組み合わせる
- 既存の英単語や個人情報を避ける
- 他のサービスとは異なるパスワードを使用
覚えやすい強力なパスワードの作り方
IPAが推奨する「フレーズ方式」を使えば、覚えやすく強力なパスワードを作れます。
手順例
- 好きなフレーズを考える:「今日はチョコレートプラスコーヒー2024年だ!」
- 頭文字を取る:「KyouhaChocolatePlusCoffee2024nenda!」
- 短縮する:「Cho+Co24!」
このようにして作ったパスワードは、本人には覚えやすく、他人には推測困難です。
絶対に避けるべき危険なパスワード
パスワード管理サービスの調査によると、以下のようなパスワードは非常に危険です。
- 「123456」「password」など単純なもの
- 「田中123」など名前と数字の組み合わせ
- 「qwerty」などキーボード配列
- 生年月日や電話番号
- 会社名や製品名
社員が守るべき!パスワード管理の基本ルール7か条
技術的な対策と併せて、社員一人ひとりが守るべき基本ルールを策定しましょう。
第1条一人一アカウントの原則
業務用アカウントの共有は原則禁止。やむを得ず共有する場合は、専用ツールを使用し、管理者の承認を得る。
第2条強力なパスワードの設定
10文字以上で、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせたパスワードを設定する。生年月日や名前などの個人情報は使用しない。
第3条パスワードの使い回し禁止
業務用と私用、異なるサービス間でのパスワード使い回しは厳禁。それぞれ固有のパスワードを設定する。
第4条安全な保管方法の徹底
パスワードをメモや付箋に書いて放置しない。やむを得ずメモする場合は、鍵のかかる場所に保管する。
第5条定期的な確認と報告
不審なアクセスや異常を発見した場合は、即座に管理者に報告する。四半期に1回、パスワードの見直しを実施する。
第6条退職時の引き継ぎ
退職や部署異動の際は、使用していた全てのアカウント情報を管理者に報告し、適切に引き継ぐ。
第7条継続的な学習
セキュリティに関する最新情報を学び、会社が実施する研修に積極的に参加する。
まとめ:安全なパスワード管理で会社を守る
パスワード管理は、中小企業にとって「コストをかけて取り組む面倒なもの」ではなく、 「会社の信用と事業継続を守る重要な投資」です。従来の「定期変更が必要」という常識が覆され、現在では強力なパスワードを設定すれば無理な定期変更は不要とされています。しかし、これは適切なツールと手順なしでのパスワード共有がリスクの高い行為であることを意味するものではありません。
中小企業においては、ツール導入だけでなく社員教育も重要な要素となります。重要度の高いシステムから順次導入することでリスクを最小化し、定期的な見直しと改善によりセキュリティレベルを維持・向上させることが求められます。現在使用している全サービスのパスワード強度をチェックし、危険なパスワードの洗い出しを行うことから始めて、無料のパスワード管理ツールでテスト運用を開始し、社員向けパスワード管理ルールの策定と緊急時対応手順の文書化を進めることが重要です。
長期的には、パスワード管理ツールの本格導入、定期的な社員研修の実施、セキュリティポリシーの策定と運用、インシデント対応体制の構築、外部専門家との連携体制の確立といった取り組みが必要となります。パスワード管理は「一度設定すれば終わり」ではありません。技術の進歩や新たな脅威に対応するため、継続的な改善が必要です。しかし、適切な対策により、 中小企業でも大企業と同等のセキュリティレベルを実現することは十分可能です。
「何から始めればよいかわからない」「自社に最適な対策を知りたい」という場合は、IT専門家に相談することをお勧めします。 小さな投資で大きな安心を得られるのが、適切なパスワード管理の最大のメリットです。会社の大切な情報と信用を守るため、今日からパスワード管理の見直しを始めてみませんか?具体的な導入支援や運用サポートについては、 株式会社テクノリレーションズまでお気軽にお問い合わせください。
ITのお困りごと、まずはお気軽にご相談ください
小田原・箱根・西湘エリアに密着。中小企業の「困った」を、電話一本で解決します。