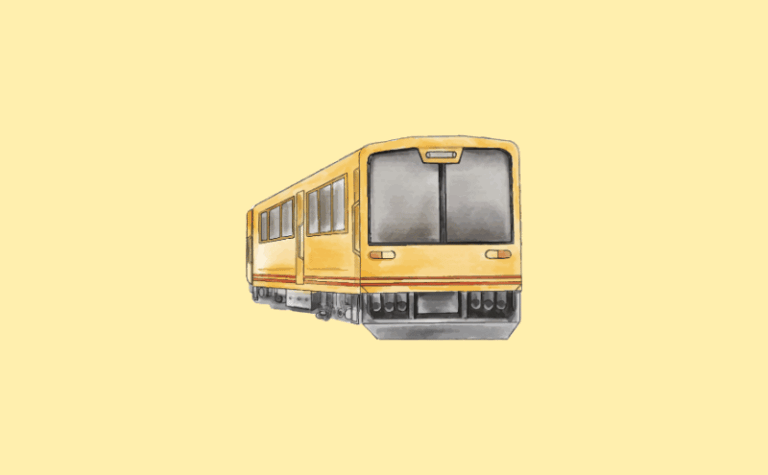目次
「競合他社が生成AIで業務効率化を進めているから、うちも導入を検討している」
「しかし、顧客情報や社内の機密データが漏れてしまったらどうしよう…」
このような悩みを抱えている中小企業の経営者は非常に多く存在します。デジタル庁が実施した「生成AIの適切な利活用に向けた技術検証」では、適切な対策により安全に活用できることが示されています。
確かに、生成AIには業務効率化という大きなメリットがある一方で、適切な対策を講じずに導入すると、以下のような深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。
- 機密情報が意図せず学習データとして使用される情報漏洩
- 生成AIが出力した誤った情報による重要な判断ミス
- 著作権侵害となるコンテンツの生成
- 従業員による無許可利用と管理の困難
- 外部からの攻撃によるシステムの不正操作
この記事では、公的機関が策定したガイドラインに基づき、ITに詳しくない中小企業の経営者でも理解できる生成AIの主要なセキュリティリスクと、今すぐ実践できる対策をわかりやすく解説します。
なぜ中小企業こそ生成AIのセキュリティリスクに注意が必要なのか
「大企業ならともかく、うちのような小さな会社は狙われないだろう」と考える経営者も多いでしょう。しかし、中小企業がむしろセキュリティリスクに注意すべき理由が明確に示されています。
中小企業がリスクにさらされやすい理由
中小企業が生成AIに関連するセキュリティ事故を起こしやすい要因として、以下の点が指摘されています。
専門人材の不足
セキュリティの専門知識を持つ人材が社内にいないため、リスクの適切な判断が困難
教育体制の未整備
生成AIの適切な使用方法やリスクについて、従業員への十分な教育が行われていない
ガバナンス体制の不備
何を行ってよく、何を避けるべきかという明確な基準が設けられていない
これらの問題の多くが「悪意のない知識不足」に起因することが報告されており、適切な対策により予防可能であることが示されています。
競争力維持のためには適切な活用が不可欠
一方で、セキュリティを恐れるあまり「生成AIを一切使用しない」という選択は、競合他社に大きく遅れをとる可能性があります。技術検証では、生成AIを適切に活用している組織で以下のような成果が確認されています
- 定型業務の処理時間短縮
- 文書作成業務の品質向上
- 新しいアイデア創出の促進
- 従業員の業務満足度向上
重要なのは「使用しない」ことではなく、「安全に使用する」ための適切な仕組みを整備することです。

【2025年最新】中小企業のAI業務効率化完全ガイド|生成AIとAIエージェントで競争力アップ
2025年中小企業向けAI導入の決定版!ChatGPT・AIエージェント活用で業務効率化を実現。補助金情報・具体的導入事例・コスト削減方法まで専門家が徹底解説。今始めないと競合に差をつけられる時代です。
ガイドラインに基づく5つのセキュリティリスク
ここからは、中小企業が特に注意すべき5つのセキュリティリスクについて解説します。
リスク1機密情報の学習データ化による情報漏洩
生成AIにより顕在化したリスクとして「機密情報の流出」が重要課題として位置づけられています。多くの生成AIサービスでは、ユーザーが入力した内容をAIの性能向上のために学習データとして活用する仕組みがあります。
なぜこのリスクが発生するのか
生成AIが学習したデータは、AIの内部に蓄積され、後に別のユーザーとの対話で類似の情報が出力される可能性があります。一度学習されたデータを完全に削除することは技術的に困難であることが指摘されています。
対策方法
- 学習機能の無効化:企業向けプランなど、学習機能を無効にできるサービスの選択
- 機密情報の明確な定義:顧客情報、契約内容、財務データなど「入力禁止情報」の具体的なリスト化
- 情報の匿名化処理:必要な場合は固有名詞を「A社」「B社」などに置き換える手法の採用
リスク2生成AIによる誤情報出力と判断ミス
生成AIが「もっともらしい誤情報」を出力する現象について詳しく分析されています。この現象は「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、重要な経営判断を誤らせる危険性があります。
リスクの技術的背景
生成AIが確率的な手法で文章を生成するため、事実性よりも自然さを優先する傾向があることが説明されています。そのため、非常に説得力のある文章でありながら、内容が事実と異なる場合があります。
対策方法
- 情報の検証義務化:AIが提供した情報は「参考意見」として扱い、公式な情報源での確認を必須とする
- 重要判断での使用制限:財務、法務、税務など、ミスが重大な影響を与える分野での利用を制限
- 複数情報源との照合:政府機関や業界団体の公式情報との比較検討を実施
リスク3著作権侵害となるコンテンツの生成
生成AIが膨大な既存コンテンツを学習しているため、既存の著作物と類似したコンテンツを生成する可能性について警告されています。知的財産権への配慮が重要な指針として示されています。
リスクの発生メカニズム
生成AIは学習データに含まれる既存の著作物の特徴を学習しており、時として既存作品と酷似した内容を生成することがあります。これを知らずに使用すると、著作権侵害として法的な問題に発展する可能性があります。
対策方法
- 生成物の独自性確認:AI生成コンテンツの使用前に、類似コンテンツの存在確認を実施
- 参考程度での活用:AIの出力をそのまま使用せず、「アイデアの出発点」として活用し、大幅な修正を加える
- 専門家への事前相談:重要な商業利用の場合は、知的財産の専門家に事前相談を実施
リスク4従業員による無許可利用と管理不能状態
明確なルールがない状態で従業員が個人の判断で様々な生成AIツールを使用することの危険性が指摘されています。これは「見えないリスク」として企業経営を脅かします。
なぜ管理不能状態が危険なのか
各従業員が異なる生成AIサービスを使用し、会社として何が行われているかを把握できない状況の危険性が報告されています。トラブル発生時の原因究明が困難になるだけでなく、意図しない情報漏洩のリスクも高まります。
対策方法
- 利用可能ツールの明確化:会社として使用を認める生成AIツールの事前決定と、それ以外の使用禁止
- 利用状況の定期報告制度:各部署での生成AI利用状況を定期的に報告する仕組みの構築
- 事前承認制の導入:新しい生成AIツールの使用時は、管理部門の承認を必須とする
リスク5外部からの攻撃による不正操作
「プロンプトインジェクション攻撃」という新しいタイプのサイバー攻撃について警告されています。これは、AIに対して悪意のある指示を混入させ、意図しない動作をさせる攻撃手法です。
攻撃の仕組み
巧妙に作られた指示により、AIが本来制限されているはずの情報を出力してしまうリスクについて技術的な解説がなされています。特に、顧客向けのAIチャットボットなどでこのリスクが高まることが指摘されています。
対策方法
- 入力内容の事前検査:悪意のある指示を検出・ブロックする仕組みの導入
- 出力内容の事後確認:AIの回答内容を人間が確認してから外部に提供する体制の構築
- アクセス権限の最小化:AIが参照できる情報の範囲を必要最小限に制限し、機密度の高い情報は除外
実践的セキュリティ対策5ステップ
リスクについて理解したところで、次は具体的な対策に移りましょう。ITに詳しくない中小企業でも実践できる段階的なセキュリティ対策をご紹介します。
ステップ1適切な生成AIサービスの選定と設定
企業での生成AI利用において、サービス選定が最も重要な初期ステップであることが強調されています。すべての生成AIサービスが同じレベルのセキュリティを提供しているわけではないため、慎重な選定が必要です。
選定基準の設定
企業向け生成AIサービスを選定する際の重要な評価項目が示されています。
- 学習機能の無効化が可能であること
- データの暗号化が適切に実施されていること
- 管理者による利用状況の監視が可能であること
- 企業データを外部に送信しない設定が可能であること
必須のセキュリティ設定項目
- 学習機能の無効化:入力データが学習に使用されない設定への変更
- データ保存場所の確認:入力・出力データの保存場所と管理方法の把握
- アクセスログの有効化:利用者、利用時間、入力内容を記録できる設定
- 管理者権限の設定:全社的な利用状況を監視できる管理者アカウントの作成
ステップ2社内利用ルールの策定
技術的な対策と同じく重要なのが、従業員が迷わず適切に生成AIを活用できるルールの策定です。ルールは複雑すぎず、誰でも理解できる内容にすることがポイントです。
基本的な利用ルールの例
利用が推奨される業務
- メール文章の草案作成(個人情報を除く一般的な内容)
- 企画書・提案書のアイデア出し(具体的な顧客名・金額を除く)
- 議事録の要約・整理(機密事項を除く)
- 社内マニュアルの文章改善
- 研修資料の作成サポート
入力が禁止される情報
- 顧客の個人情報(氏名、住所、電話番号など)
- 契約書の具体的な内容
- 財務情報、売上データ
- システムのパスワードやアクセス情報
- 競合他社から得た機密情報
注意が必要な業務
- 法律・税務に関する質問(専門家確認が必須)
- 外部公開予定のコンテンツ作成(著作権確認が必須)
- 数値計算やデータ分析(結果の検証が必須)
ステップ3従業員教育と意識向上
どれだけ良いルールを作成しても、従業員が理解し実践しなければ意味がないことが強調されています。定期的な教育と意識向上の取り組みが不可欠です。
効果的な従業員教育方法
- リスク事例を用いた研修:他組織での情報漏洩事例を紹介し、「なぜ問題になったのか」を具体的に説明
- 適切な使用例の共有:生成AIを適切に活用して成果を上げた社内事例の紹介
- 定期的なリマインド:朝礼や会議での生成AI利用ルールの定期確認
- 相談しやすい環境作り:「この使用方法は適切か?」と気軽に相談できる担当者の設置
従業員の理解度確認項目
以下の質問に全従業員が正しく答えられるよう、継続的な教育を実施しましょう。
- 会社で使用が認められている生成AIサービスは何か?
- 顧客情報を生成AIに入力してはいけない理由は?
- 生成AIの回答をそのまま使用してはいけない場面は?
- 新しい生成AIツールを使用したい場合の手続きは?
- 生成AI関連で困った時の相談先は?

その”油断”が命取り!小田原・箱根の中小企業のための”やさしい社内セキュリティ教育”入門
小田原・箱根地区の中小企業向け。「パスワード使い回し」「怪しいメールのクリック」など社員の"うっかり"が情報漏えいに。旅館・製造業・飲食店でも今日から始められる社内セキュリティ教育の進め方を解説。
ステップ4定期的な利用状況の監視と見直し
生成AI活用は継続的なプロセスであることが示されています。定期的に利用状況を確認し、問題がないかをチェックする仕組みを構築しましょう。
月次確認項目
- 利用状況の把握:各部署でどのような生成AI活用が行われているか
- トラブルの有無:不適切な使用や問題の発生がなかったか
- ルールの遵守状況:設定したガイドラインが守られているか
- 新たなニーズの把握:追加で必要な機能やツールはないか
四半期ごとの見直し項目
- セキュリティ設定の確認:使用中の生成AIサービスに新しいセキュリティ機能が追加されていないか
- 利用ルールの更新:業務の変化に応じてルールの修正が必要か
- 従業員教育の効果測定:理解度や意識レベルに問題はないか
- 新技術への対応:新しい生成AIツールや機能の導入を検討すべきか
ステップ5インシデント対応体制の構築
万が一、生成AIの利用に関連してセキュリティ問題が発生した場合に備え、迅速に対応できる体制を事前に整えておくことの重要性が示されています。
インシデント対応の基本手順
- 初動対応(発見から30分以内):問題の規模を把握し、必要に応じて該当生成AIツールの利用を一時停止
- 影響範囲の調査(1時間以内):漏洩した可能性のある情報の種類と範囲を特定
- 関係者への報告(2時間以内):経営陣、必要に応じて顧客・取引先への連絡
- 対策の実施(24時間以内):被害の拡大防止と根本原因の除去
- 再発防止策の検討(1週間以内):ルールや体制の見直し・改善
緊急連絡体制の整備
生成AI関連のセキュリティ問題が発生した際の連絡体制を事前に決めておきましょう。
- 社内責任者:生成AI利用の最終責任者(経営陣または管理部門長)
- 技術担当者:生成AIツールの設定変更や停止を実行できる人材
- 外部専門家:法的相談や技術的サポートを受けられる連絡先
- 顧客対応担当:必要に応じて顧客への説明を行う責任者
外部専門家との連携による安心・安全な生成AI活用
「社内にITの専門知識を持つ人材がいない」「自社だけでセキュリティ対策を実施するのは不安」という中小企業には、外部の専門家との連携が推奨されます。専門知識を持つ外部パートナーとの協力の重要性が示されています。
IT支援会社に依頼できるサービス内容
生成AI利用環境の構築・設定
適切な生成AIツールの選定から初期設定まで、専門家がサポートします。
- 業務内容に最適な生成AIツールの選定
- セキュリティ設定の実施・確認
- 社内ネットワークとの安全な連携設定
- 利用状況監視システムの構築
社内ルール・ガイドライン策定
業種や企業規模に応じた、実践的な生成AI利用ルールを作成します。
- 業務フローに合わせたルール設計
- リスクレベルに応じた利用制限の設定
- 緊急時対応手順の策定
- 定期見直しのスケジュール作成
従業員向け研修・教育
生成AI利用の基本から応用まで、従業員のスキルレベルに応じた研修を実施します。
- 生成AIの基本知識とリスク理解
- 適切な利用方法の実習
- トラブル事例を使った注意喚起
- 継続的なスキルアップサポート
まとめ:安心・安全な生成AI活用に向けて
生成AIは確かに便利なツールですが、適切な理解と対策なしに使用すると、深刻なセキュリティリスクを招く可能性があります。しかし、ガイドラインに基づいた適切な対策を段階的に実施することで、中小企業でも安心して生成AIを活用することができます。
重要なのは「禁止」ではなく「適切な活用」を目指すことです。段階的・継続的な取り組みで着実にレベルアップし、必要に応じて外部専門家の力を借りながら、セキュリティリスクを適切に管理しつつ、積極的に生成AIを活用していくことが重要です。
「まずは何から始めればよいかわからない」「現在の利用状況に不安がある」といった場合は、一人で悩まず、専門家に相談することをお勧めします。株式会社テクノリレーションズでは、中小企業の皆様が安心して生成AIを活用できるよう、丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。