目次
「雷でパソコンが落ちて、3時間分の受注データが全部消えた…」
都内の卸売業A商事様(従業員15名)で実際に起きた出来事です。夏の夕立による瞬間停電で、入力中の受注データが消失しました。顧客への確認作業に丸一日かかり、約50万円の売上機会を失うという深刻な事態となりました。
あなたの会社は大丈夫ですか?地震、雷、近所の工事など、予期せぬ停電は意外と身近な脅威です。業界調査によると、年商10億円規模の企業でサーバーダウンが発生した場合、1日あたりの損失額は数百万円に達するケースがあります。
そんな事態を防ぐ方法はいくつかありますが、その中でも UPS(無停電電源装置)は有効な対策の一つです。本当に必要なのか、他に方法はないのか、詳しく解説します。
UPS(無停電電源装置)とは?基本的な仕組み
UPS(Uninterruptible Power Supply)は、停電時に瞬時に電源を切り替え、一定時間機器へ電力を供給し続ける装置です。通常時は商用電源から機器に電力を供給しつつ、同時にUPS内蔵のバッテリーに充電を行います。そして停電などの非常時には、バッテリーから各機器に給電することで、一瞬も止めることなく電気を供給し続けられるのです。
UPSには3つの重要な保護機能があります。まず、作業中のファイル保存時間を確保することでデータを保護します。次に、システムを安全にシャットダウンさせることで機器の故障を防止します。そして最後に、ネットワークを維持することで、取引先への影響を最小限に抑えます。
ただし、長時間の停電には耐えられません。システムの安全なシャットダウンや発電機が起動するまでの繋ぎとして利用するのが現実的です。
中小企業にUPSは本当に必要?判断のポイント
多くの中小企業でUPSが必要と考えられる理由は、現代の業務がITシステムに深く依存しているからです。受発注データを扱う商社や卸売業、顧客データベースを管理する企業、設計図面やCADデータを扱う製造業、会計や経理データを扱う全ての企業では、 データ損失が致命的な影響をもたらします。
また、ECサイト運営会社やコールセンター、在庫管理システムに依存する小売業、オンライン会議が多い企業では、業務停止そのものが大きな損失に直結します。さらに、BtoB取引がメインの企業や納期管理が厳格な業界、継続的なサービス提供が求められる企業では、取引先への信頼が重要であり、停電による業務中断は信用失墜につながりかねません。
一方で、完全にクラウドベースで作業を行い、停電時も業務に支障がない企業、データ損失のリスクが極めて低い企業、復旧に時間がかかっても問題ない企業では、UPS導入の優先度は下がるかもしれません。しかし、多くの中小企業では前者に該当するのが実情です。
クラウド時代の停電対策|ネットワーク機器こそ重要
「うちはGoogleドキュメントだから自動保存されるし、停電対策は不要でしょ?」そう考える経営者も少なくありません。確かにクラウドサービスは自動保存されますが、クラウド時代だからこそ、ネットワークが生命線になっています。
停電で起こる本当の問題は、ルーター停止による全社インターネット接続断絶、Wi-Fiアクセスポイント停止による無線環境の完全停止、スイッチングハブ停止による社内ネットワーク分断、モデム停止による外部との通信完全遮断です。 データはクラウドにあっても、アクセスできなければ意味がありません。

税理士・社労士向けITツール完全ガイド|業務効率3倍UP術
残業続きの税理士・社労士必見!クラウド会計ソフト・RPA活用で仕訳作業を60%削減。一人事務所でも導入できる低コストITツール選びから導入手順まで専門家が解説。今すぐ使える業務効率化ノウハウを無料公開中。
ネットワーク機器へのUPS導入がもたらす効果
クラウドサービスが主流となった現在、個々のPCよりもネットワーク機器へのUPS導入の方が効果的である可能性があります。ルーター1台を保護することで全社の通信を継続でき、全PCに導入する場合と比較して圧倒的に安価な投資で済みます。また、集中管理により運用負荷が軽減され、停電時でも全従業員がインターネットを利用できるという分かりやすい効果を実現できます。
BCP(事業継続計画)の観点からUPSを考える
近年、自然災害による停電リスクが急増しています。台風は年々大型化し広域停電が頻発、地震では送電設備の損傷による長時間停電、夏季は雷による局地的停電の主要因となっており、工事や事故による予期せぬ瞬間停電も発生しています。
UPSによるBCP強化効果は多岐にわたります。リスク軽減面では、データ損失リスクの大幅削減、機器故障リスクの回避、業務中断時間の最小化が図れます。事業継続性向上の観点では、重要業務の継続可能性、顧客サービスレベルの維持、復旧時間の大幅短縮が期待できます。組織的メリットとしては、従業員の心理的安心感、経営陣の危機管理意識向上、取引先からの信頼度アップも重要な要素です。
BCP策定時のUPS位置づけは段階的に考えるべきです。まずリスク評価で停電による業務への影響度を評価し、対策立案でUPSによる停電対策を検討、体制構築で停電時の対応手順を策定、最後に訓練と改善で定期的な停電対応訓練を実施します。
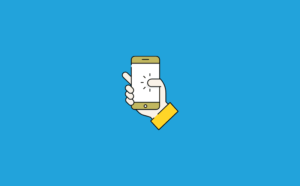
【緊急警告】社用スマホのウイルス感染が急増中!「5つのウイルスに感染しています」は本物?BYOD対策の完全ガイド
社用スマホのウイルス感染対策とBYOD運用の完全ガイド。「5つのウイルスに感染しています」偽警告の見分け方から緊急対応マニュアルまで、ランサムウェア被害が5年連続1位、中小企業が64%を占める現状を統計で解説。Android/iPhone別セキュリティ設定、VPN対策、2段階認証の導入方法を実例付きで紹介。
UPSの限界とデメリット|知っておくべき現実
UPSは万能ではありません。まず、瞬断の問題があります。商用電源からバッテリーへの切り替えに数ミリ秒かかるため、精密機器が瞬断を検知して停止する場合があります。この対策には常時インバーター方式のUPSが必要ですが、高額になります。
長時間停電への限界も深刻です。バッテリー容量に限界があり、通常5~30分程度しか持続できません。東日本大震災時のように数日間の停電が発生すれば、結局機器は停止してしまいます。
メンテナンスの負担も考慮すべき点です。バッテリーの劣化により、鉛蓄電池では2~5年で交換が必要となり、定期点検も年1回程度推奨されています。また、UPS自体の故障による停電リスクも存在します。
設置・運用の制約として、24時間稼働により室温が上昇し、ファンの音が気になる場合もあります。それなりの設置面積も必要で、すでに非常用発電機がある企業、クラウドのみで一切のローカルデータがない企業、停電時は業務停止が当然と割り切れる企業、コスト対効果が見合わない零細企業では、UPS導入が適さない場合もあります。
UPS以外の停電対策|他の解決方法を検討
停電対策はUPS以外にも複数の選択肢があります。
自動保存・クラウド化の徹底
UPSより低コストでメンテナンス不要、どこからでもアクセス可能というメリットがあります。Google WorkspaceやMicrosoft 365の活用、自動保存間隔を最短に設定、ローカルファイルの完全排除などが具体的方法です。ただし、ネットワーク停止時はアクセス不可、通信速度に依存、セキュリティ面での不安というデメリットもあります。
非常用発電機の導入
長時間の停電にも対応し、全社の電力を一括でカバー、冷暖房も含めた完全対応が可能です。しかし、導入コストが極めて高額(数百万円から)で、燃料の定期補給が必要、騒音や排気の問題があります。
モバイル環境の充実
停電時も業務継続可能で、災害時の事業継続性向上、働き方改革にも寄与します。社用スマートフォンやタブレットの配布、モバイルWi-Fiルーターの導入、クラウドベース業務システムの構築などが具体的な手法です。ただし、通信費が継続的に発生し、画面が小さく作業効率が低下、セキュリティ管理が複雑というデメリットがあります。
ポータブル電源による停電対策
最近注目されているポータブル電源は、従来のUPSとは異なるアプローチで停電対策を実現します。大容量バッテリーにより数時間から丸一日の電源供給が可能で、災害時や長時間停電にも対応できます。
ポータブル電源のメリットは、大容量で長時間の電源供給が可能なこと、持ち運びができて災害時にも活用できること、平常時はアウトドアや非常時の備えとしても使えることです。一方でデメリットとして、切り替え時間がUPSより長いため重要なサーバーには適さない場合があること、こまめな充電管理が必要なこと、すべての製品がUPS機能を持つわけではないことが挙げられます。
業務の分散化
単一障害点の排除、リスクの分散効果、柔軟な働き方の実現が可能になります。在宅勤務制度の導入、サテライトオフィスの設置、業務のデジタル化とペーパーレス化などの方法があります。
現実的な停電対策の組み合わせ
実際の対策では、複数の手法を組み合わせることが重要です。
小規模企業向けの最小限対策では、クラウド化徹底とネットワーク機器のみのUPSで、投資額5~10万円程度で基本的な業務継続性を確保できます。
一般的中小企業向けの標準対策では、重要PC・サーバーにUPS、クラウド化、モバイル環境の組み合わせで、投資額20~50万円程度で高い事業継続性を実現できます。
重要インフラ企業向けの完全対策では、非常用発電機、全社UPS、冗長化システムで、投資額数百万円以上で完全な事業継続性を目指します。

Windows 10終了まで残り約2ヶ月!中小企業のPC買い替え緊急対策ガイド
Windows 10サポート終了まで残り約2ヶ月。中小企業が今すぐ取るべき対策を専門家が解説。アップグレード・買い替え・クラウド化の3つの選択肢と具体的な手順を詳しく紹介します。
まとめ|最適な停電対策を選ぼう
停電対策に「絶対的な正解」はありません。企業の規模や業務内容、予算に応じて最適な組み合わせが異なります。
まず検討すべきはネットワーク機器の保護です。クラウド時代において、インターネット接続の維持は全社の業務継続に直結します。次に、重要なサーバーやデータベース、顧客対応が止められない業務への対策を検討しましょう。
UPSにも限界があり、ポータブル電源や他の対策も含めて総合的に判断することが重要です。完璧を求めるより、現実的で継続可能な対策から始めてください。
停電は予告なしにやってきます。今こそ、あなたの会社に最適な停電対策を検討する時です。

