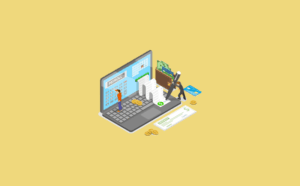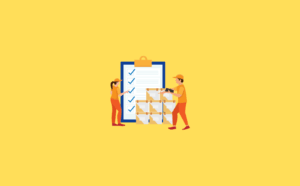【小田原・箱根の経営者必見】ITツールが社内で定着しない7つの理由| 観光業・製造業・士業の地域企業向け完全ガイド

「予約管理システムを入れたのに、結局スタッフが紙の台帳に戻ってしまった」、「クラウド会計ソフトを契約したものの、税理士とのやり取りは相変わらずメール添付のまま」、「社内チャットツールを導入したのに、連絡は電話とFAXばかり」
小田原・箱根エリアの中小企業経営者から、こうしたご相談が増えています。観光業や製造業、士業など、業種を問わず「 ITツールを導入したのに現場で使われない」という課題に直面している企業が少なくありません。
実際に、神奈川県西部地域の中小企業では、ITツール導入後の定着率が全国平均と比較してやや低い傾向にあります。その背景には、業種特有の働き方、世代間のITリテラシーの差、そして地域独特の商習慣が複雑に絡み合っています。
この記事では、小田原・箱根エリアの中小企業に特化して、ITツールが定着しない7つの理由と、実際に地域企業で成功した導入事例、さらには神奈川県西部で活用できる実践的な内容を解説します。
なぜ小田原・箱根エリアでITツールが定着しないのか?地域特有の背景
小田原・箱根エリアの企業がITツール定着に苦戦する背景には、地域特有の事情があります。まず、観光業が盛んな地域であるため、旅館やホテル、飲食店など「おもてなし」を重視する企業が多く、デジタル化よりも対面でのサービスが優先される文化があります。
また、製造業においても、熟練の職人技術を重視する企業が多く、「現場の勘と経験」が尊重される風土があります。こうした環境では、ITツールは「余計なもの」と捉えられがちです。
さらに、神奈川県西部地域の中小企業では、従業員の年齢層が幅広く、60代のベテラン社員と20代の若手社員が同じ職場で働くことも珍しくありません。世代間でのITリテラシーの差が大きいため、「若手は使えるけど、ベテランが使えない」という二極化が起こりやすいのです。
小田原・箱根エリアで起こりやすいIT導入の失敗パターン
箱根の老舗旅館
予約管理システムを導入したが、仲居さんたちが操作方法を覚えられず、結局予約台帳に手書きで記録
小田原の製造業
生産管理システムを入れたが、現場の職人が「パソコンは苦手」と紙の作業指示書を使い続ける
地元の税理士事務所
クラウド会計を顧客に勧めたが、顧客側の高齢経営者が使いこなせず、結局従来通りの紙ベースに戻った
観光施設
多言語対応の受付システムを導入したが、スタッフが日本語でしか対応できず、機能を持て余している
ITツールが社内で定着しない7つの理由
小田原・箱根エリアの企業で、ITツールが定着しない理由を7つに整理しました。自社に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
理由1導入目的が現場に伝わっていない
経営者や管理職が「業務効率化のため」と思ってツールを導入しても、現場の社員には「なぜこれを使わなければいけないのか」が理解されていないケースが非常に多くあります。
特に、長年同じ方法で仕事をしてきたベテラン社員にとって、新しいツールは「余計な手間」としか感じられません。「今までのやり方で困っていないのに、なぜ変える必要があるのか」という疑問が解消されないまま、ツールだけが導入されても定着するはずがありません。
小田原市内のある製造業では、生産管理システムを導入した際、経営者は「在庫の見える化」を目的としていましたが、現場の作業員には「面倒な入力作業が増えただけ」としか伝わっておらず、結局使われなくなってしまいました。
理由2操作が難しすぎる、または複雑すぎる
高機能なツールほど、操作が複雑になりがちです。特にITに慣れていない社員にとって、ログイン方法から始まり、メニューの選び方、データの入力方法、保存の仕方など、すべてが「壁」になります。
箱根のある旅館では、多機能な予約管理システムを導入しましたが、画面の項目が多すぎて、どこをクリックすればいいのかわからず、スタッフが混乱してしまいました。結果的に、若手スタッフだけが使える状態となり、ベテランの仲居さんたちは従来の紙の予約台帳に戻ってしまいました。
ITツールは「使いやすさ」が何よりも重要です。どれだけ高機能でも、現場が使いこなせなければ意味がありません。
理由3業務フローとツールがマッチしていない
汎用的なツールは便利ですが、自社の業務フローに合っているとは限りません。特に、観光業や製造業など、業種特有の業務フローがある場合、一般的なツールでは対応しきれないことがあります。
例えば、小田原の水産加工業者では、在庫管理システムを導入しましたが、「生鮮食品の賞味期限管理」や「日々変動する仕入れ価格」に対応できず、結局エクセルでの管理に戻ってしまいました。ツールが業務に合っていなければ、どれだけ優れたシステムでも定着しません。
理由4使い方を教える時間と人材がいない
中小企業では、IT専任の担当者がいないことがほとんどです。そのため、新しいツールを導入しても、「誰が教えるのか」「いつ教えるのか」が明確でなく、結局「自分で覚えてね」で終わってしまいます。
特に、観光業では繁忙期と閑散期があり、忙しい時期に新しいツールの使い方を覚える余裕はありません。また、製造業でも納期に追われている現場では、「今はそれどころじゃない」となりがちです。
理由5トラブル時のサポート体制がない
「使っていてわからないことがあったら誰に聞けばいいのか」が明確でないと、社員は不安でツールを使いたがりません。特に、ITに不慣れな社員ほど、「間違った操作をしたらデータが消えるのでは」「システムが壊れるのでは」といった不安を抱えています。
小田原市内の税理士事務所では、クラウド会計ソフトを導入しましたが、顧客から「操作方法がわからない」という問い合わせが殺到し、事務所スタッフが対応に追われる事態になりました。サポート体制が整っていないまま導入すると、かえって業務負担が増えてしまいます。
理由6経営者自身がツールを使っていない
意外と見落とされがちですが、経営者自身がツールを使っていないと、社員も「本当に必要なのか」と疑問を持ちます。特に中小企業では、経営者の姿勢が社内文化に大きく影響します。
「社員には使わせるけど、自分は使わない」という姿勢では、社員のモチベーションは上がりません。実際に、箱根のある観光施設では、経営者がメールすら使わず、すべて紙とFAXで指示を出していたため、社員も「デジタル化は必要ない」と感じてしまい、導入したツールが全く活用されませんでした。
理由7導入後のフォローアップがない
ツールを導入した直後は、社員も「使わなければ」という意識がありますが、時間が経つにつれて元の方法に戻ってしまうことがよくあります。これは、導入後の定期的なフォローアップや振り返りがないためです。
小田原市内のある製造業では、勤怠管理システムを導入しましたが、最初の半年は使われていたものの、それ以降は紙のタイムカードに戻ってしまいました。定期的に「使い方を振り返る」「困っていることを聞く」といったフォローがなければ、ツールは定着しません。
社員に使ってもらえる導入7ステップ
ステップ1導入前に現場の声を聞く
まず最初にやるべきことは、「現場の困りごと」を丁寧に聞くことです。経営者や管理職が「これが便利だろう」と思って導入しても、現場が求めているものと違えば使われません。
具体的には、以下のような質問を現場に投げかけてみましょう:
- 今の業務で一番面倒だと感じることは何か?
- もし改善できるなら、どの作業を楽にしたいか?
- 紙やエクセルで管理していることで困っていることはあるか?
- 他部署との情報共有でストレスを感じることはあるか?
この段階で現場の本音を引き出すことで、「本当に必要なツール」が見えてきます。
ステップ2ツールの目的と期待効果を明確に伝える
「なぜこのツールを使うのか」を、全員が納得できる形で説明することが重要です。単に「業務効率化のため」では伝わりません。具体的な数字やメリットを示しましょう。
例えば:
- 「このシステムを使えば、予約確認の時間が1日30分短縮できます」
- 「在庫管理をデジタル化すれば、発注ミスが減り、無駄な在庫を持たなくて済みます」
- 「情報共有ツールを使えば、いちいち電話で確認する手間が省けます」
現場にとっての「自分ごと」になるように伝えることがポイントです。
ステップ3シンプルなツールを選び、機能を絞る
高機能なツールは魅力的ですが、最初から全機能を使いこなそうとすると失敗します。まずは「これだけ使えばOK」という機能を1〜2個に絞りましょう。
例えば:
- 予約管理システムなら「予約確認」と「顧客情報の閲覧」だけ
- 社内チャットなら「連絡事項の投稿」と「既読確認」だけ
- クラウド会計なら「領収書のアップロード」だけ
慣れてきたら徐々に他の機能も使うようにすれば、段階的にレベルアップできます。
ステップ4わかりやすいマニュアルを作る
マニュアルは「文字だらけの説明書」ではなく、「見ればすぐわかる手順書」にしましょう。おすすめは以下の方法です:
- 画面のスクリーンショットを使い、どこをクリックするか矢印で示す
- A4用紙1枚に収まる分量にする
- 動画マニュアルを作成し、スマホでも見られるようにする
- 「困ったときのQ&A」を別紙で用意する
特に、ITに不慣れな社員には、動画で実際の操作を見せることが効果的です。5分程度の短い動画を作成し、何度も見返せるようにしておきましょう。
ステップ5社内に相談できる人を配置する
「わからないことがあったら誰に聞けばいいか」を明確にしておくことが大切です。理想は、各部署に1名ずつ「ITサポーター」を配置することです。
ITサポーターの役割:
- 操作方法の質問に答える
- トラブルが起きたときの一次対応
- 新しい便利な使い方を見つけたら社内に共有
- 定期的にミニ勉強会を開催
ITサポーターには、特別なスキルは必要ありません。「人に教えるのが好き」「ITに抵抗がない」程度の人材で十分です。
ステップ6定期的な振り返りとフォローアップ
導入して終わりではなく、定期的に「使えているか」「困っていることはないか」を確認する場を設けましょう。おすすめは以下のタイミングです:
- 導入後1週間:初期の混乱を解消するための臨時ミーティング
- 導入後1ヶ月:使用状況の確認と、追加で必要なサポートの検討
- 導入後3ヶ月:定着度合いの評価と、次のステップの計画
- その後は四半期ごと:継続的な改善と新機能の追加検討
振り返りの場では、「できていないこと」を責めるのではなく、「どうすればもっと使いやすくなるか」を一緒に考える姿勢が重要です。
ステップ7外部の専門家に相談する
社内だけで解決できない場合は、外部のITサポート会社に相談するのも有効な選択肢です。ただし、「設定だけして終わり」ではなく、「現場が使えるようになるまで伴走してくれる」会社を選ぶことが重要です。
外部サポートに依頼すべきケース:
- 社内にIT担当者がいない、またはITに詳しい人がいない
- 複数のツールを連携させる必要がある
- セキュリティ対策も含めて総合的に相談したい
- 業種特有の業務フローに合わせたカスタマイズが必要
- 従業員が多く、全員への教育が難しい
小田原・箱根エリアには、地域企業の実情を理解したITサポート会社があります。地域密着型の支援を受けることで、スムーズな導入が可能になります。
まとめ|ITツール定着は「仕組み」と「伴走支援」がカギ
小田原・箱根エリアの中小企業でITツールを定着させるためには、ツールの選定だけでなく、「現場が使いたくなる環境作り」が不可欠です。
導入目的を明確に伝え、シンプルな機能から始め、社内にサポート体制を整えることが成功への近道です。また観光業、製造業、士業など、それぞれの業種に合ったツール選定と、地域特有の商習慣を理解した導入支援が重要です。
「せっかく導入したツールが使われない」という悩みは、正しいステップを踏み、現場に寄り添った支援を行えば必ず解決できます。自社に合ったITツールの選定や導入方法についてお困りの際は、お気軽に テクノリレーションズまで気軽にご相談ください。