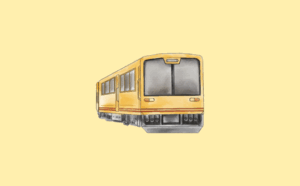AIに“まかせきり”は危険?中小企業がChatGPT導入前に決めておくべき3つのルール

「ChatGPTを業務で使いたいけど、どこまでOKにすべきか迷っている」
そんな声を多く聞くようになりました。特に中小企業では、ルールが曖昧なまま社員がAIを使い始めてしまい、後から慌てて対応するケースが増えています。
この記事では、ChatGPTなどの生成AIを導入する前に、中小企業が最低限決めておくべき“3つの基本ルール”をご紹介します。「うちにはまだ早い」と思っている会社こそ、今のうちにルールを整備しておくことで、安心して業務に活用できる土台が作れます。
なぜAI導入に“ルール作り”が欠かせないのか?
生成AIの精度は日々進化していますが、それでも「絶対に正しい情報が返ってくる」とは限りません。しかも、AIは自信満々に“もっともらしい間違い”を返してくることがあります。
社内でルールがないまま導入すると、以下のような問題が発生しやすくなります。
- 社員が知らずに機密情報を入力してしまう
- AIの回答をそのままコピペしてトラブルになる
- AI利用の責任の所在が不明瞭で、誰も注意できない
技術そのものよりも、“どう運用するか”が企業のリスクを左右する時代になっています。
1. 機密情報・個人情報を入力しないルール
ChatGPTなどの生成AIは、入力した内容を学習に利用する可能性があります。たとえ最新の「プライバシー設定」があっても、完全に情報漏えいを防ぐことはできません。
よって、社内資料・顧客情報・パスワード・見積書・契約書などの入力は控えた方がよいかもしれません。このあたりもルールとして文書化し、口頭説明だけで終わらせないことが大切です。
たとえば弊社では、社員に「AIに入力してはいけない情報リスト」を配布しています。教育コストは一度で済み、社内の安心感も高まりました。
2. 「使っていい業務」「使ってはいけない業務」を明確にする
「どこまでAIに任せてよいのか」が曖昧なままでは、判断が分かれ、社内トラブルにつながります。
たとえば以下のように、活用可能な範囲を事前に定めておきましょう。
- OK:案内文のたたき台作成、議事録の要約、FAQの草案づくり
- NG:最終的な契約書の作成、顧客への送信メールの自動生成、判断が必要な助言
活用は“下書きまで”にとどめ、最終確認は必ず人間が行うルールを徹底します。
とくに社外文書は「誤解のない表現」「会社としての責任を伴う表現」が求められるため、AIによる下書きを活用する場合も、あくまで“ベース作り”にとどめ、文章全体を自社らしい言葉に整える必要があります。
3. 相談できる体制をつくる
AIの活用を“個人任せ”にせず、「困ったときに相談できる」仕組みを持つことが重要です。
たとえば
- 「AI活用に詳しい社員」を決めておく
- 気になる事例や改善アイデアを共有できるチャットルームを作る
- 月1回のミニ勉強会や情報共有タイムを設定する
「社内に聞ける人がいる」安心感が、AI活用のハードルを下げます。兼任でも構わないので、窓口的な役割を設けておくと効果的です。
現実的にすべての履歴を残すのは難しいため、運用の中で気づきや改善点を“社内ナレッジ”として少しずつ蓄積していく仕組みづくりが望まれます。
補足|AIツール利用の社内ポリシー例
以下は、ある中小企業が定めたChatGPT活用ポリシーの抜粋です。
- 業務での使用は、原則として「下書き作成」に限る
- 顧客情報・社内機密・パスワードなどの入力は禁止
- 出力内容の最終チェックは必ず人が行う
- 活用の注意点は社内マニュアルに記載・共有
- 月次MTGで活用状況と改善点を共有する
ポリシーを作って終わりにせず、定期的な見直しと教育が重要です。
まとめ|ルールがあるから、AIは安心して使える
生成AIは、中小企業にとって大きな業務効率化の武器になりますが、正しく使わなければリスクも伴います。
導入前に「最低限のルール」を定めておくことで、社員の混乱や誤用を防ぎ、安全に運用することができます。
ChatGPTをはじめとしたAIは、あくまで“補助ツール”です。人の判断や責任と切り離さずに活用することで、はじめて真の効果を発揮します。
株式会社テクノリレーションズでは、ChatGPTを含むAI導入の相談・活用ルール作成の支援も行っています。「まだ使っていないけれど気になっている…」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。