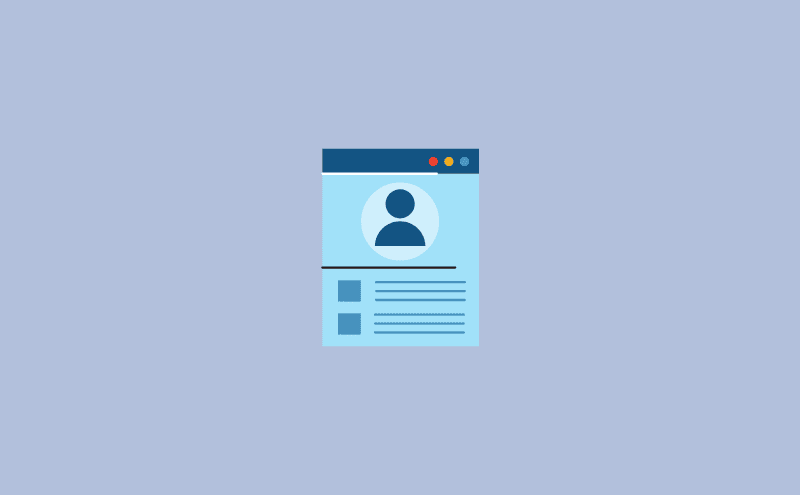目次
「最近、誰がどのツールを使っているのか分からなくなってきた」──そんな声を、中小企業の経営者からよく耳にします。ITツールの導入が進む一方で、アカウント管理が追いつかず、思わぬトラブルや情報漏えいにつながるケースが増えています。
本記事では、アカウント管理の重要性と中小企業が陥りがちな課題、そして具体的な対策について、背景や事例、ツール紹介を交えながら、ITに不慣れな方にも分かりやすく丁寧に解説します。
なぜ“アカウント管理”が重要なのか?
クラウドサービスや業務アプリの導入が当たり前になっている現在、多くの中小企業でも「Google Workspace」「Dropbox」「Chatwork」などのツールを活用していることでしょう。
しかし、その一方で「退職した社員のアカウントが有効なまま」「誰がどのツールの管理者か不明」「複数のパスワードが共有されたまま」といった状態になっていないでしょうか。
このような状況は、サイバー攻撃のリスクや内部不正を誘発する大きな原因となります。特に中小企業では、IT管理が“なんとなく”進められがちで、属人化や口頭伝達に頼った運用がされていることが少なくありません。
たとえば、ある建設業の企業では、前任者が作った管理用スプレッドシートの存在を誰も知らず、退職者のDropboxが1年近く放置されていました。後にそのアカウントから元社員が顧客情報を誤って閲覧したことで、クレームにつながったケースもあります。
アカウント管理は、ツールの“裏方”ではありますが、会社全体の情報セキュリティと生産性の根幹を支える仕組みです。たとえるなら、建物に鍵があっても「誰が持っているか分からない」状態では防犯にならないのと同じです。
よくあるアカウント管理の失敗例とその背景
中小企業で見られるアカウント管理の失敗は、決して特殊な話ではありません。代表的な失敗例とその原因を、以下に整理してみましょう。
- 退職者アカウントの放置:退職手続きのたびにIT対応が後回しにされ、アカウント削除が忘れられる。
- 個人名アカウントの多用:「takahashi.y@〜」のような個別アカウントが管理されず、引き継ぎが困難。
- パスワードの紙管理:メモ帳や付箋に記載されたパスワードが放置され、誰でも閲覧できる。
- 部門ごとに異なる運用:営業部はExcel、総務部はGoogleで管理、統一感がない。
こうした背景には「IT管理は詳しい人がなんとかしてくれるだろう」という思い込みがあり、明確なルールや担当が設定されていないことが挙げられます。
また、「小さな会社だからそこまでしなくても」と思いがちですが、情報漏えいや業務混乱は企業規模に関係なく起こります。逆に小規模な組織こそ、一つのアカウントトラブルが経営に与える影響が大きいのです。
“見える化”から始めるアカウント管理のステップ
では、どのようにすれば「管理されている状態」に近づけることができるのでしょうか。初めてアカウント管理に取り組む企業でも、以下の5ステップでスタートできます。
- 使用中のITツールの一覧を作成する:まずは、現在社内で使っているすべてのツール・アプリを棚卸ししましょう。
- アカウントの所有者・用途を記録する:各アカウントが誰に使われ、何の目的で利用されているのかを記載します。
- 管理者アカウントを明確にする:各サービスで「管理者」となっているアカウントを特定し、必要に応じて整理します。
- 退職者・休職者の利用履歴を確認:過去の社員が利用していたアカウントの状況をチェックし、停止・削除を行いましょう。
- アカウント発行・削除のルールを作る:今後の入社・退社に備えて、運用ルールを文書化します。
これらはExcelやGoogleスプレッドシートでも対応できますが、件数が増えてくると属人的な運用に限界がきます。その場合は、資産管理ツールやIT台帳ツールの導入を検討するのも有効です。
おすすめのツールと運用例
具体的には、以下のようなツールを活用すると、運用の「抜け漏れ」や「見落とし」を防ぐことができます。
- Google Workspace:アカウントの一括管理、アクセス権限設定、ログ監査が可能。中小企業に最も広く利用されています。
- 1Password / Bitwarden:パスワードを安全に保管・共有できるツール。管理者権限でチームごとの閲覧範囲設定が可能。
- Asset Penguin / 管理クラウド:IT資産やアカウントを一覧で管理でき、期限や更新状況も自動で通知される。
ツールを導入する際は、「導入しただけ」で終わらせず、どのように社内で使っていくかのルール整備と、全員への共有が重要です。
社内定着のための教育と工夫
どんなに優れたルールやツールがあっても、現場で運用されなければ意味がありません。そこで欠かせないのが、以下のような「定着の工夫」です。
- 紙よりも動画でマニュアルを作る(例:5分のスマホ視聴可能な説明動画)
- 操作手順は「Q&Aノート」形式で社内に共有
- 新人研修にアカウント運用の基本を組み込む
また、社内に1人でも「ITのことを相談できる人」がいれば、それだけで心理的ハードルが下がります。たとえば「IT推進係」や「Google管理者」といった役割を設け、月に一度のチェックを実施するのもおすすめです。
社員のITスキルはさまざまです。すべての社員がエンジニアのように詳しくなる必要はありません。大切なのは「自分の担当範囲を守る」ためのルールを、誰でもわかる形で用意することです。
支援事例:医療機関のアカウント統合プロジェクト
実際に、弊社が支援したある医療機関では、80名の職員が複数のクラウドサービスを利用していたにもかかわらず、管理者が不在でした。
退職者のGoogleアカウントが1年以上アクティブで、Drive上には顧客の個人情報が残ったまま。外部アクセスの危険性も高まっている状態でした。
そこで、以下のプロセスで改善支援を実施しました:
- アカウントの棚卸しと統一命名ルールの導入
- 全アカウントをGoogle管理者コンソールで一元管理
- 退職・異動時のチェックリスト作成
- 動画マニュアルと社内勉強会による定着サポート
結果として、1ヶ月で管理者不明アカウントがゼロになり、毎月の点検プロセスも標準化されました。「何かあってもすぐ対応できる安心感がある」とご評価をいただいています。
まとめ|アカウント管理は“守り”と“攻め”を両立する要
アカウント管理というと、つい「面倒」「後回し」にされがちですが、これは会社の“デジタル玄関”を守る重要な施策です。
一つの放置アカウントが、取引先の信頼を損なう原因になり得ることを忘れてはなりません。逆に、しっかりとした管理体制を整えれば、業務効率化・セキュリティ強化・BCP対策にもつながります。
「何から手をつければいいか分からない」という方は、まずは自社で使っているツールの一覧を紙に書き出すところから始めてみてください。
株式会社テクノリレーションズでは、中小企業に最適なアカウント管理の設計・導入・教育まで、ワンストップで支援しています。ぜひお気軽にご相談ください。