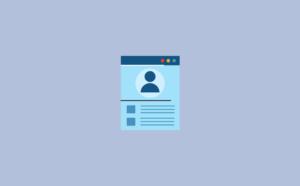IT担当者ゼロでもできる!中小企業のための最低限セキュリティ対策マニュアル

中小企業の経営者の方から、「IT担当者がいないから、セキュリティ対策は後回しにしている」というご相談をよくいただきます。
ですが、IT担当者がいない企業こそ、最低限のセキュリティ対策を急ぐべきです。攻撃者は「防御が甘い企業」を狙っているため、何も対策していない会社はリスクが高くなります。
この記事では、IT担当がいない中小企業でも実践できる、シンプルかつ効果的なセキュリティ対策を5つご紹介します。また、なぜ中小企業が狙われやすいのか、その背景とあわせて、事故が起きた際の初動対応についても解説します。
なぜ”最低限のセキュリティ対策”が必要なのか?
「うちは小さい会社だから大丈夫」と思っていませんか?
実は、サイバー攻撃の7割以上は中小企業をターゲットにしています。理由は明確で、大企業に比べて対策が甘いからです。
攻撃者にとっては、セキュリティが甘い中小企業を狙った方が、短時間で大きな成果を得られる可能性があります。たとえば、重要な取引先の情報、顧客リスト、請求書データなど、小さな会社でも貴重な情報を持っていることが多く、それらが漏洩すれば甚大な被害につながります。
さらに、中小企業は情報漏洩によるダメージからの回復が難しい傾向があります。社会的信用を失うと、取引停止や契約解除に発展し、最悪の場合、廃業に追い込まれるケースもあるのです。
IT担当ゼロでもできる!最低限のセキュリティ対策5選
-
すべてのPC・スマホにパスワードロックをかける
まずは物理的なアクセスを防ぐことが基本です。パスワードなしで使える端末は、盗難・紛失時に大きなリスクになります。
実際に、パスワード設定をしていなかったPCが盗難され、顧客データが漏洩してしまった事例もあります。パスワードは8文字以上で、英字・数字・記号を組み合わせる強固なものを設定しましょう。
-
OS・アプリを常に最新状態に保つ
セキュリティホール(脆弱性)は、アップデートでふさぐことが前提になっています。
特に、古いOS(例:Windows7)を使い続けている場合、サポート切れによる重大なリスクがあります。社内ルールとして「毎週金曜日にアップデートを確認する」といった運用を設けましょう。
-
業務データはクラウドに保存する
PC本体にしかデータがないと、故障やウイルス感染ですべてのデータを失うリスクがあります。
Google Drive、Dropbox、OneDriveなど、法人利用が可能なクラウドサービスを選び、二段階認証も必ず設定しましょう。また、共有範囲を限定し、誰がどのデータにアクセスできるかも管理することが重要です。
-
メールの添付ファイルは安易に開かない
ウイルスの多くはメール経由で感染します。特に、”知らない送信元”や”違和感のある日本語”がある場合は、添付ファイルを開かず削除しましょう。
たとえば、「請求書の確認をお願いします」と書かれた不審メールに添付されていたファイルを開いた結果、ランサムウェアに感染してしまった中小企業の例もあります。
社員向けに「怪しいメールの特徴」をまとめたガイドラインを作成し、定期的に教育しましょう。
-
社内の”ルール”を決めておく
「知らなかった」ではすまされないのが情報漏洩リスクです。最低限、以下のような社内ルールを文書化して共有しましょう。
- パスワードの設定・管理ルール
- クラウドサービス利用ルール
- 社外持ち出しデバイスの取り扱いルール
- ウイルス感染が疑われる場合の初動対応フロー
ルールは1回作ったら終わりではなく、年に1回程度は見直し・アップデートするのが理想です。
【コラム】セキュリティ事故が起きたとき、まず何をすべき?
万が一、ウイルス感染や情報漏洩が発覚した場合、慌てず冷静に以下を実行しましょう。
- 被害端末のネットワーク接続をすぐ切断する
- 上司または管理者に速やかに報告する
- 感染範囲や漏洩範囲を調査する
- 必要に応じて外部専門家(ITサポート会社)に連絡する
- 顧客・取引先への報告フローを確認し、適切に対応する
初動対応を誤ると、被害が拡大するだけでなく、後々の責任追及リスクも高まります。あらかじめ対応マニュアルを作成し、社内共有しておきましょう。
まとめ|”できるところから”でいい。まず一歩を
完璧なセキュリティを一気に目指す必要はありません。まずは”できることから”確実に始めることが大切です。
社員数が少ない会社ほど、一人のミスが全社に影響を及ぼします。だからこそ、小さな対策でも”続ける”ことが重要です。
セキュリティ対策は”コスト”ではなく、”事業を守るための最低限の保険”です。後悔する前に、今日から一歩踏み出しましょう。
株式会社テクノリレーションズでは、IT担当がいない企業様向けに、実践的なセキュリティ対策支援も行っています。無理なく始めるためのご相談、いつでも承っています。