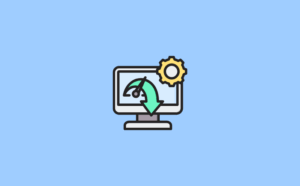“引き継ぎが口頭だけ”はもう限界!業務属人化を防ぐテンプレート管理法

「この作業、前任者に聞いてやってたけど、もう辞めちゃって聞けない…」、「何度も同じことを教えてる気がする…」、「結局、あの人しかやり方を知らないから休めない…」
こんな“あるある”に、思い当たる節はありませんか?
中小企業では、人数が限られている分、特定の人に業務が集中=属人化しやすいのが現実です。
そして、その状態を放置していると、引き継ぎ時の混乱・業務ミス・生産性の低下など、さまざまな問題が表面化していきます。
この記事では、口頭だけの引き継ぎから脱却し、業務を“見える化”して属人化を防ぐ「テンプレート管理」の方法を、実践形式でご紹介します。
なぜ「属人化」が起きてしまうのか?よくある3つの原因
まずは、なぜ中小企業では属人化が起きやすいのか、その原因を整理してみましょう。
1. 業務が「人についている」状態
中小企業では「この仕事は○○さんの担当」といった形で、仕事内容がその人の頭の中にしか存在しないことがよくあります。
この状態が長く続くと、「○○さんがいないとできない仕事」が増えてしまい、休みづらい・辞められない・教えられない、という悪循環に。
2. 教え方が「その場の口頭指示」だけ
作業を教えるときに、「画面見ながらちょっと説明する」「近くでやって見せる」といった方法が主流になっている場合、再現性のある“やり方の記録”が残りません。
そのため、次の人が学ぼうとしたときに「あれ、どうやってたっけ?」と混乱するのです。
3. 業務の優先順位や全体像が“見えない”
特に属人化している業務は、「この処理がどこにつながっているか」が不明瞭なケースが多く、引き継ぎの際に“抜け漏れ”が起きやすくなります。
つまり、作業手順だけでなく、「この仕事の目的」「全体の流れ」「どこに報告するか」といった周辺情報も含めて伝える仕組みが必要なのです。
属人化で実際に起こる“困った”事例
では、属人化を放置していると、どんなトラブルが起きてしまうのでしょうか?
事例1「辞めた社員しか知らない作業」で業務がストップ
ある中小企業では、経理担当者が辞めた後に「請求書の締め方」「入金チェックの方法」が分からず、入金確認が遅れて請求ミスに発展しました。
その社員は「全部頭で覚えてたからマニュアルない」と言って退職しており、復元までに2週間かかりました。
事例2「あの人に聞いて」が繰り返される非効率な社内
ある営業部では、在庫の確認・納期調整・伝票処理などが特定の社員に集中。
その人が休みの日は誰も分からず、「○○さん戻ってきたら確認しよう」と時間のロスや二度手間が頻発していました。
事例3「見よう見まね」でミスが多発、信用失墜へ
現場作業の報告書を新人が書くようになったが、やり方を「前の人のファイルを見て覚えて」と言われた結果、表現ミスや記録漏れが続出。
取引先から「品質管理ができていない」と指摘され、信頼を損なってしまいました。
テンプレートで業務を「見える化」するメリットとは?
属人化の解消には、「業務の流れ」「使う書類」「判断の基準」などを誰でも確認できるようにすること、つまり業務の“見える化”が欠かせません。
そのための最も簡単な方法が、「テンプレート管理」です。
テンプレートとは?
テンプレートとは、業務に必要な“ひな型”をあらかじめ用意しておくことです。
報告書のフォーマット、見積もりメールの定型文、マニュアルの章立てなど、繰り返し使う情報を統一フォーマットで管理します。
テンプレート管理のメリット
- 誰がやっても同じ形式で進められる(属人化を防げる)
- 抜け漏れ・記入ミスが減る(品質が安定する)
- 説明の時間が減る(教育工数の削減)
- 書類のチェックがラクになる(上司の負担軽減)
- 社内にノウハウが蓄積される(組織力が上がる)
テンプレートがあると、何が変わる?
「この報告書ってどう書けばいいんですか?」「どこに保存すればいいですか?」といった“何をどうしたらいいか分からない”が一気に減少します。
また、「前任者が辞めたら何も分からなくなる…」という不安からも解放され、引き継ぎもスムーズになります。
今日から始められる!テンプレート管理の進め方ステップ
では、実際にテンプレート管理を導入するとき、どのように進めればよいのでしょうか?
特別なシステムは不要。まずはGoogleドキュメントやExcelで十分です。
STEP1まずは1つだけ、繰り返し業務を選ぶ
「週報」「請求書作成」「報告書」など、何度も同じ形式でやっている業務から着手するのがコツ。
最初から完璧を目指す必要はありません。まずは1つ、「毎月使えるフォーマットを残す」ことを目標にします。
STEP2今使っている資料をひな形にする
誰かが使っていた過去の資料をベースに、「毎回書く部分」と「毎回変わる部分」を分けて整理します。
項目名・記入例・提出先・保存場所などを明記しておくと、誰でも使いやすくなります。
STEP3保存場所を社内共通にする(Google Driveなど)
テンプレートは「共有フォルダ」の中に「テンプレート専用フォルダ」を作って保存しましょう。
ファイル名には【テンプレート】のようなプレフィックスをつけておくと検索もしやすくなります。

STEP4使うタイミングでテンプレを複製して運用
実際の業務では、テンプレートを「複製」して使います。
オリジナルを上書きしないようにし、「テンプレからコピーして使う文化」を社内に定着させることがポイントです。
STEP5更新・改善は“気づいた人が更新”ルールで
テンプレートを作ったあとも、改善点が見つかれば都度修正していきましょう。
「更新履歴」を記録しておけば、いつ・誰が・何を変えたかも管理しやすくなります。
導入に成功した中小企業の事例
事例1業務マニュアルが紙1枚に。「新人研修の時間が半分に」
神奈川県の製造業A社では、新人への業務説明に毎回ベテラン社員の時間が取られており、担当者からも「効率が悪い」との声がありました。
そこで、毎週提出する報告書や伝票処理などの定型業務をテンプレート化し、Googleスプレッドシートで一覧管理する仕組みを導入。
その結果、マニュアル確認だけで業務が理解できるようになり、ベテラン社員の時間も半減。新人教育の負担が軽減されました。
事例2「業務の属人化」から「分担できる職場」に変化
サービス業のB社では、1人の事務員が経理・請求・メール対応すべてを行っており、休みが取りづらい状況でした。
退職のタイミングで業務内容を洗い出し、すべてテンプレート化(やること・提出先・納期などを明記)したところ、3人で分担できる体制に。
属人化していた業務が共有化され、有給休暇の取得もしやすくなったといいます。
事例3作業の“手順忘れ”によるミスがゼロに
小売業のC社では、「毎月の棚卸報告の数字が合わない」という問題がありました。
作業手順が担当者の記憶頼りだったため、「やり方が違っていた」「報告内容がバラバラ」などの属人化が原因でした。
そこで、「棚卸チェックリスト」をテンプレートとして導入し、スマホから確認・入力できるようにしたところ、作業ミスと確認工数が大幅に減少。
パートスタッフにも「やりやすい」「同じ手順で安心」と好評でした。

まとめ|テンプレートで「誰でもできる」を当たり前にする
「やり方を口で説明するだけ」「聞けばわかるでしょ」──そんな現場のやりとりは、忙しいとき・人が変わったとき・急な退職時に大きなリスクになります。
テンプレートを使えば、「誰でも、いつでも、同じ品質で業務ができる」状態をつくることができます。
それはミスの削減や業務の効率化だけでなく、社員の安心感や、組織全体の力の底上げにもつながります。

株式会社テクノリレーションズでは、業務棚卸しからテンプレート設計・社内共有の仕組みづくりまでを一貫してサポートしています。
「とりあえず前任者に聞く文化を変えたい」「テンプレートで仕組み化したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。