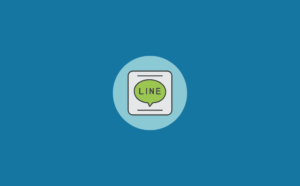【中小企業経営者必見】電車内でパソコンを開くリスクと情報漏洩を防ぐ対策ガイド
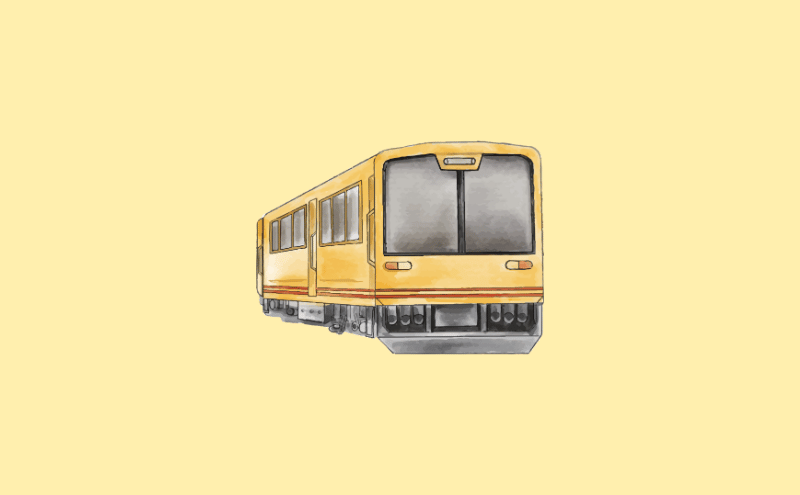
朝の通勤電車で、ノートパソコンを広げてメールチェックや資料作成をしている人を見かけることが増えました。「移動時間を有効活用したい」「お客様への返信を急ぎたい」そんな気持ちは、とてもよく分かります。
しかし、電車内でのパソコン作業には、想像以上に深刻なリスクが潜んでいることをご存じでしょうか。特に中小企業では、たった一人の何気ない行動が会社全体の信用失墜につながる可能性があります。
実際に、以下のような「ヒヤリハット」が日常的に発生しています。
- 電車内でメールを確認していたら、隣の人に顧客名が見えていた
- コーヒーを飲みながら営業資料を見ていて、知らないうちに撮影されていた
- 駅のフリーWi-Fiを使ったら、後日不正アクセスの痕跡が見つかった
- 電車で居眠りして、パソコンを置き忘れそうになった
- 混雑で押されて、パソコンを落としそうになった
この記事では、ITに詳しくない経営者の方でも理解できるよう、電車内でのパソコン利用リスクと、今日からできる具体的な対策を分かりやすく解説します。
公的機関も警告:電車内パソコン作業の深刻なリスク
総務省が公表している「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」では、モバイル勤務(移動中を含む勤務)における情報セキュリティリスクについて詳細に警告されています。特に電車内のような公共空間での作業は、組織の情報セキュリティにとって重大な脅威となることが明記されています。
また、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表する「情報セキュリティ10大脅威2024」では、「不注意による情報漏えい等の被害」が6位にランクインしており、前年の9位から大幅に順位を上げています。これは、移動中を含む様々な場面での情報管理の重要性が増していることを示しています。
「のぞき見」による情報漏洩の実態
電車内でのパソコン作業で最も多いリスクが「ショルダーハッキング」と呼ばれる、画面ののぞき見による情報漏洩です。満員電車でなくても、隣や向かいの席から画面が見えてしまうことは珍しくありません。
特に危険なのは以下のような状況です。
- 顧客リストや営業資料を表示している時:会社名、担当者名、取引金額などが第三者に見える
- メールのやり取りを確認している時:送信者名、件名、本文の一部が読み取られる
- パスワード入力の瞬間:キーボード操作から重要な認証情報が読み取られる
- 社内資料や企画書を閲覧している時:事業戦略や機密情報が漏れる
フリーWi-Fiに潜む「見えない脅威」
総務省の「無線LANの安全な利用について」では、公共Wi-Fiの利用リスクが詳細に解説されています。電車内や駅構内で提供される便利なフリーWi-Fiサービスには、深刻なセキュリティリスクが潜んでいます。
最も危険なのは「偽装Wi-Fi」の存在です。悪意のある第三者が正規のWi-Fiと似た名前のネットワークを設置し、利用者の通信内容を盗み見る手口が確認されています。例えば、正規の「JR-EAST-FREE-Wi-Fi」に対して「JR-EAST-Wi-Fi」といった紛らわしい名前のネットワークが設置されることがあります。
フリーWi-Fi経由で以下のような情報が漏洩するリスクがあります。
- メールの送受信内容
- ウェブサイトのログイン情報
- クラウドサービスへのアクセス内容
- 社内システムへの接続情報
物理的な紛失・盗難リスク
電車内では、パソコンの物理的な紛失や盗難のリスクも無視できません。朝の通勤ラッシュでの押し合いや、居眠りによる注意力の低下、緊急停車時の混乱など、様々な要因でパソコンを手放してしまう可能性があります。
実際に報告されている事例として、以下があります。
- 居眠りして目が覚めたら、隣に置いていたパソコンが盗まれていた
- 急停車でパソコンが床に落ち、故障して大切なデータが消失した
- 下車時の混雑で荷物を忘れ、パソコンを置き忘れた
- 痴漢騒動の混乱に乗じて、パソコンが盗まれた
パソコンには、顧客情報、取引先データ、社内の機密資料など、企業にとって重要な情報が保存されています。これらの情報が第三者の手に渡れば、情報漏洩による損害賠償、信用失墜、取引停止など、深刻な経営リスクに直結します。
今すぐ実践できる電車内パソコン利用の安全対策3選
リスクを理解したうえで、それでも移動中の作業が必要な場合があります。ここでは、ITに詳しくない方でも今日から実践できる、具体的で効果的な対策をご紹介します。
対策1のぞき見防止フィルターで物理的な盗み見を完全ブロック
最も簡単で効果的な対策が「のぞき見防止フィルター」の活用です。パソコン画面に貼るだけで、正面以外からの視認性を大幅に低下させることができます。
のぞき見防止フィルターは、特殊な材質により、正面から見ると通常通り画面が見えるのに、横や斜めから見ると真っ黒に見えるという仕組みです。まるで「マジックミラー」のような効果で、隣の席からの盗み見を物理的に防ぐことができます。
選び方のポイントとして、以下があります。
- 画面サイズの正確な測定:インチ数だけでなく、実際の縦横サイズを測って選ぶ
- 視野角の確認:30度、45度、60度など、どの角度から見えなくなるかを確認
- 着脱の容易さ:毎日使うものなので、簡単に付け外しできるタイプを選ぶ
- 画面の見やすさ:フィルター装着時の画面の明るさや色合いを事前に確認
価格は2,000円~6,000円程度で、家電量販店やインターネットで簡単に購入できます。一度購入すれば長期間使用でき、情報漏洩リスクを考えると非常にコストパフォーマンスの高い投資といえます。
対策2フリーWi-Fiを避けてテザリングまたはVPNを活用
電車内や駅でのインターネット接続は、フリーWi-Fiではなく、より安全な方法を選択することが重要です。
最も簡単で安全な方法は、スマートフォンのテザリング機能を使うことです。テザリングとは、スマートフォンを「Wi-Fiルーター」として使い、パソコンをインターネットに接続する機能です。
設定方法は以下の通りです。
- スマートフォンの「設定」を開く
- 「インターネット共有」または「テザリング」を選択
- 「Wi-Fiパスワード」を設定(他人に推測されない複雑なものにする)
- パソコンのWi-Fi設定で、スマートフォンの名前を選んで接続
ただし、テザリングはスマートフォンのデータ通信量を消費するため、契約プランに応じて使用量を調整する必要があります。
VPN(仮想プライベートネットワーク)の導入も効果的です。VPNとは、インターネット上に「専用の暗号化された通信路」を作るサービスです。まるで「透明なトンネル」の中を通信が行き来するイメージで、第三者による盗聴を防ぐことができます。
VPNの主なメリット
- 通信内容が暗号化され、盗聴リスクが大幅に低下
- 偽装Wi-Fiに接続してしまっても、情報が保護される
- 会社のIPアドレスからのアクセスとして認識される
- 地理的制限のあるサービスにも安全にアクセスできる
対策3「電車内作業ルール」で安全な業務範囲を明確化
個人の判断に委ねるのではなく、会社として「電車内でできる作業」と「してはいけない作業」を明確に定義することが重要です。
電車内でも比較的安全な作業
- 個人情報を含まない社内資料の閲覧
- パスワード入力が不要な情報収集
- 既に作成済みの文書の読み返し
- スケジュール確認(詳細な顧客情報が表示されないもの)
注意が必要な作業
- 顧客名が表示される営業資料の確認
- 件名に機密情報が含まれるメールの確認
- 取引金額や条件が記載された書類の閲覧
- 社内向けの企画書や提案書の作成
電車内では絶対に避けるべき作業
- パスワードを必要とするシステムへのログイン
- 顧客の個人情報や機密情報の閲覧・編集
- 銀行口座やクレジットカード情報へのアクセス
- 重要な契約書や法的文書の確認
- 人事情報や給与データの処理
万が一情報漏洩が発生した場合の初動対応手順
どれだけ対策を講じても、人間のミスや予期せぬ事故により情報漏洩が発生する可能性をゼロにすることはできません。重要なのは、事故が発生した際の迅速で適切な初動対応です。
情報漏洩の疑いが発生した場合、最初の1時間の対応が被害の拡大を左右します。以下の手順を事前に整理し、全従業員が把握しておくことが重要です。
- 被害の確認と報告:何が、どの程度漏洩したかを可能な範囲で確認し、直ちに上司・経営陣に報告
- 二次被害の防止:関連するシステムへのアクセス停止、パスワードの変更、該当端末のネットワーク切断
- 証拠の保全:パソコンの状態保持、関連するログの収集、目撃者の確認
- 影響範囲の特定:漏洩した情報に含まれる顧客数、情報の種類、機密度の確認
- 関係機関への連絡:警察(盗難の場合)、顧問弁護士、保険会社への第一報
迅速な対応を行うためには、事前に緊急連絡網を整備し、全従業員が把握している必要があります。
- 社内緊急連絡先:経営陣、部門責任者、IT担当者の24時間連絡可能な電話番号
- 外部専門機関:顧問弁護士、IT系専門業者、保険会社の緊急連絡先
- 公的機関:最寄りの警察署、個人情報保護委員会、業界の監督官庁
- 重要顧客:機密情報を多く扱う主要顧客の緊急連絡先

社内教育で徹底する「移動中セキュリティ」の意識向上
技術的な対策と並んで重要なのが、従業員全体のセキュリティ意識向上です。特に中小企業では、専門のIT担当者がいない場合が多いため、全従業員が基本的なセキュリティ知識を身につける必要があります。
年に2回以上、電車内でのパソコン利用リスクに特化した社内研修を実施することを推奨します。研修では、以下の内容を含めることが重要です。
- 実際の事故事例の紹介:同業他社で発生した情報漏洩事故とその影響
- 自社ルールの確認:電車内作業の可否判断基準の再確認
- 対策ツールの使い方:のぞき見防止フィルターやVPNの正しい使用方法
- 緊急時対応の練習:情報漏洩発見時の報告手順の実践練習
研修だけでなく、日常的にセキュリティ意識を維持する仕組みも重要です。
- 月次チェックリスト:電車内作業時の安全対策実施状況を月1回確認
- 事例共有会:他社の事故事例や新しい脅威情報を定期的に共有
- 相互チェック制度:同僚同士で外出時の安全対策をチェックし合う
- 改善提案制度:従業員からのセキュリティ改善アイデアを積極的に採用
新しく入社した従業員には、通常の業務研修に加えて、移動中セキュリティに関する特別教育を実施します。
- 自社の情報管理ポリシーの詳細説明
- 電車内作業の実地シミュレーション
- セキュリティツールの実際の使用体験
- 緊急時連絡先の確認と連絡方法の練習

【実践例】成功している中小企業の電車内セキュリティ対策
実際に効果的な電車内セキュリティ対策を実施している中小企業の事例をご紹介します。これらの事例は、同様の規模・業種の企業にとって参考になるはずです。
従業員20名の税理士事務所では、外回りの多い環境で移動中の情報管理が課題となっていました。実施した対策
- 全スタッフにのぞき見防止フィルター付きのノートPCを支給
- 電車内では「顧客情報の表示禁止」を社内ルール化
- VPN接続必須とし、フリーWi-Fi使用を禁止
- 月1回の安全管理ミーティングで事例共有
結果として、導入から2年間情報漏洩事故ゼロを継続し、顧客からの信頼度も向上して新規顧客獲得にもプラスの効果がありました。
従業員50名の建設会社では、現場と事務所を往復する営業担当者の移動中作業で、設計図面や見積書の管理が課題でした。実施した対策
- 設計図面や見積書は専用クラウドサービスで管理
- 電車内では「閲覧のみ」「編集は事務所のみ」のルール設定
- スマートフォンのテザリング機能を全営業担当者に導入
- 四半期ごとのセキュリティ教育を実施
結果として、情報管理の効率化と安全性向上を両立し、競合他社への情報流出リスクが大幅に軽減されました。
従業員10名のソフトウェア開発会社では、プログラムソースコードや顧客システムの仕様書など、高度な機密情報の移動中管理が課題でした。実施した対策
- 機密度に応じた情報分類システムを導入
- 「最高機密」レベルの情報は電車内アクセス完全禁止
- リモートデスクトップによる安全な社内システムアクセス
- 全端末に自動ログ取得システムを導入
結果として、顧客からのセキュリティ監査でも高評価を獲得し、大手企業からの受注機会が増加しました。
まとめ:安全で効率的な働き方の実現に向けて
電車内でのパソコン作業は、移動時間の有効活用という点で大きなメリットがありますが、同時に深刻な情報漏洩リスクも伴います。中小企業にとって、情報漏洩事故は企業存続に関わる重大なリスクです。
重要なのは、以下の3つのポイントです。
- 技術的対策の確実な実施:のぞき見防止フィルターの装着、安全な通信手段の利用、適切なクラウドサービスの活用
- 社内ルールの明確化と教育:電車内作業の可否判断基準の策定、定期的な従業員教育の実施、緊急時対応手順の整備と訓練
- 万が一への備え:情報漏洩保険・サイバー保険への加入検討、外部専門業者との連携体制構築、継続的なリスク評価と対策見直し
適切な対策を講じることで、電車内でのパソコン作業のリスクを大幅に軽減することが可能です。まずは基本的な対策から始めて、徐々にセキュリティレベルを向上させていくことが重要です。
電車内でのパソコン作業を完全に禁止する必要はありませんが、そのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで、安心して移動中の時間を活用することができます。
具体的な対策の導入方法や、自社の状況に応じたセキュリティポリシーの策定については、 株式会社テクノリレーションズまでお気軽にお問い合わせください。