【緊急警告】社用スマホのウイルス感染が急増中!「5つのウイルスに感染しています」は本物?BYOD対策の完全ガイド
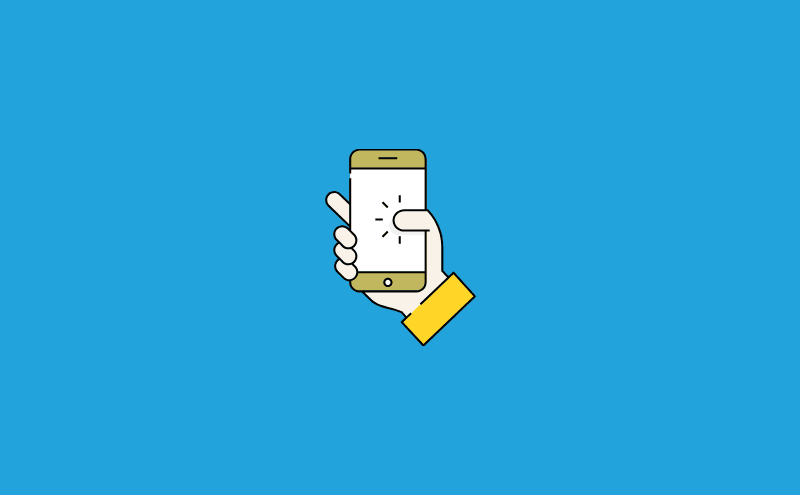
「5つのウイルスに感染しています」「お使いのスマートフォンがハッキングされました」──こんな警告画面を社員のスマホで見かけたことはありませんか?
実は、これらの多くは偽警告ですが、本当のウイルス感染も急増しているのが現実です。
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が2025年1月に発表した「情報セキュリティ10大脅威2025」では、ランサムウェアが10年連続で組織向け脅威の第1位に選ばれています。特に中小企業では、社員が個人のスマートフォンで業務を行う「BYOD(Bring Your Own Device)」が当たり前となっている今、たった1台の社用スマホのウイルス感染が会社全体のデータを危険にさらすケースが後を絶ちません。
社用スマホのウイルス感染、こんな被害が実際に発生しています
警察庁の統計によると、2023年のランサムウェア被害件数は197件で、高水準で推移しています。
- ランサムウェア被害:警察庁が2024年3月に発表したサイバー犯罪レポートによると、2023年のインターネットバンキング不正送金被害は5,578件、被害総額は約87億3,130万円で、いずれも過去最多でした。
- 顧客情報漏洩:取引先のメールアドレスや電話番号が流出
- なりすまし詐欺:感染したスマホから偽メールが大量送信される
- 不正アクセス:クラウドの重要ファイルが削除・改ざんされる
この記事では、社用スマホのウイルス対策からBYOD運用の完全ガイドまで、中小企業の経営者が知るべき対策を徹底解説します。
「5つのウイルスに感染しています」の正体と対処法
この警告の90%は偽物です!でも油断は禁物
スマートフォンに突然表示される「5つのウイルスに感染しています」「今すぐウイルス駆除が必要です」という警告画面。これらの大半は、ユーザーを騙して偽のアプリをダウンロードさせる詐欺手法です。
偽警告の特徴
- 突然全画面で表示される
- 「今すぐ対処しないと大変なことに」と煽る
- アプリのダウンロードを促す
- バイブレーションや音で驚かせる
正しい対処法
やるべきことは、ブラウザを即座に閉じること(バックキーまたはホームボタン)、ブラウザの履歴とキャッシュを削除すること、信頼できるセキュリティアプリでスキャン実行すること、念のため重要なアカウントのパスワード変更を行うことです。
絶対にやってはいけないのは、警告画面の指示に従うこと、推奨アプリをダウンロードすること、電話番号に連絡すること、クレジットカード情報を入力することです。
でも注意!本当のウイルス感染も増加中
偽警告が多いからといって、本当のウイルス感染がないわけではありません。特に社用スマホでは、以下のような真のセキュリティ脅威が急増しています。
社用スマホがウイルス感染する5つのパターン
パターン1メール添付ファイルからの感染
最も多いのが、取引先を装った偽メールの添付ファイルからの感染です。「請求書」や「契約書」といった業務関連のファイル名で送られてくるExcelやPDFファイルの中には、開くだけで感染する悪質なものが存在します。
このような攻撃を防ぐには、送信者の確認を徹底することが重要です。いつもやり取りしている取引先からでも、いつもと文体が異なる、緊急性を煽る内容、不自然な日本語などの特徴があれば要注意です。不審な添付ファイルは開く前に、必ず電話などの別の手段で送信者に確認を取りましょう。
パターン2偽アプリのダウンロード
「業務効率化アプリ」や「セキュリティ強化アプリ」を装った偽アプリによる感染も急増しています。特に公式ストア以外からアプリをインストールしたり、QRコードやリンクから直接誘導される不正アプリに注意が必要です。
対策として、アプリのダウンロードは必ずGoogle PlayやApp Storeなどの公式ストアからのみ行い、インストール前にはアプリのレビューと開発者情報を確認しましょう。また、使わなくなったアプリは定期的に削除することで、セキュリティリスクを軽減できます。
パターン3フリーWi-Fiでの中間者攻撃
カフェや駅などの無料Wi-Fiを業務利用する際の「中間者攻撃」も深刻な脅威です。攻撃者が偽のWi-Fiスポットを設置し、接続してきた端末の通信内容を盗聴・改ざんするケースが報告されています。
このリスクを避けるため、業務での公衆Wi-Fi利用は原則禁止とし、やむを得ない場合はVPN接続を必須としましょう。可能な限りモバイル通信(4G/5G)を積極的に活用することが安全です。

パターン4SNSやメッセージアプリ経由
LINEやFacebookメッセンジャーなどのSNSアプリを通じた攻撃も増加しています。「友達」からの偽メッセージや不審なリンクを通じて、ソーシャルエンジニアリング攻撃が仕掛けられることがあります。
業務用途では、SlackやMicrosoft Teamsなどの専用ビジネスアプリを使用し、プライベートSNSでの業務情報共有は避けましょう。また、たとえ知人からのメッセージでも、不審なリンクはクリックしないよう徹底することが重要です。
パターン5OSやアプリの脆弱性を悪用
古いOSバージョンの脆弱性や、セキュリティパッチが適用されていない端末を狙った攻撃も多発しています。特にサポートが終了した端末や、自動アップデートを無効にしている端末は格好の標的となります。
これを防ぐには、OSとアプリの自動アップデートを有効にし、常に最新バージョンを保つことが不可欠です。サポートが終了した端末は業務利用を停止し、定期的にセキュリティパッチが適用されているかを確認しましょう。
BYOD対策の基本:まず押さえるべき6つのポイント
1. 端末管理最低限のセキュリティ要件を設定
社用スマホを安全に運用するためには、まず基本的なセキュリティ設定が欠かせません。画面ロックは6桁以上のパスコードまたは生体認証を必須とし、自動ロック時間は5分以内に設定しましょう。また、端末紛失時に備えてリモートワイプ機能を有効にし、OSとアプリの自動アップデートを常に最新状態に保つことが重要です。
これらの設定は一度行えば自動的に維持されるため、手間をかけずに高いセキュリティレベルを保てます。特にOS の自動アップデートは、新たな脅威に対する防御として非常に効果的です。
2. ウイルス対策:携帯端末にセキュリティアプリは本当に必要?
多くの企業が疑問に思うのが「スマートフォンにもウイルス対策ソフトが必要なのか」という点です。結論から言えば、業務利用するなら必須と考えるべきでしょう。
Android端末の場合
一部の調査では、国内のAndroid端末を狙ったマルウェアは2019年比で約2倍の検出数が報告されています。Android端末では、iPhoneと比べてアプリの審査が緩く、悪意のあるアプリが紛れ込む可能性が高くなります。
iPhone(iOS)の場合
Appleの公式見解によると、「iPhoneとiPadでは、すべてのアプリはApp Storeから取得され、かつサンドボックス化されます。これにより、ウイルス、マルウェア、不正な攻撃などを過度に心配することなく、Appleデバイス上のアプリに安心してアクセスできるようになります」とされています。
実際に、iPhoneのセキュリティ設計では各アプリをそれぞれ固有の仮想スペース(サンドボックス)で実行するため、ウイルスがアプリケーション間で拡散することが困難になっています。また、App Storeの厳格な審査により、マルウェアに感染したアプリがダウンロードできる状態になる可能性は極めて低いとされています。
ただし、業務利用においては、Wi-Fi監視やフィッシング対策、不正サイトブロックなどの追加機能を考慮すると、セキュリティアプリの導入価値は十分にあります。特にBYODでは、個人利用と業務利用が混在するため、より高いセキュリティレベルが求められます。
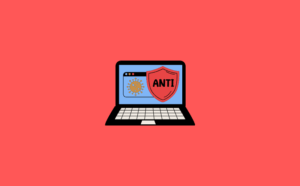
3. アクセス管理:2段階認証の全面導入
業務で使用するすべてのクラウドサービスには、2段階認証の設定が不可欠です。Google Workspace や Microsoft 365 はもちろん、Dropbox や OneDrive などのクラウドストレージ、社内システムや業務アプリ、メールアカウントすべてを対象とします。
2段階認証により、たとえパスワードが漏洩しても、不正アクセスを防ぐことができます。設定は初回のみで、その後の利用に大きな負担はありません。
4. データ保護:社用データの適切な管理
重要なデータは端末ではなくクラウドに保存することを原則とし、定期的なデータ同期とバックアップを行います。保存データは暗号化し、アクセス権限は最小権限の原則に従って設定します。
端末に重要データを保存しないことで、紛失や盗難時のリスクを大幅に軽減できます。また、クラウド上でのアクセス制御により、不正利用を防ぐことも可能です。
5. ネットワーク:安全な通信環境の確保
ランサムウェア感染経路の最新統計を見ると、深刻な状況が浮き彫りになります。ランサムウェアの感染経路は警視庁の調査によると、VPN機器やリモートデスクトップ経由が約85%を占めています。
これらの数字が示すのは、テレワーク環境で導入されたセキュリティ上の不備を突かれるケースが圧倒的に多いということです。社外からアクセスする際はVPN接続を必須としながらも、そのVPN機器自体のセキュリティ管理が不十分では本末転倒になってしまいます。
導入機器や利用者の棚卸し、認証情報の管理、修正プログラムの適用、脆弱性への対策といった基本的な管理を確実に行う必要があります。また、すべての通信はSSL/TLS暗号化を確認し、ファイアウォールによる不正アクセス防止も重要です。
特に中小企業では、2024年上半期のランサムウェア被害の約64%を占めているという統計もあり、大企業と比べてセキュリティ対策が不十分になりがちな傾向があることが数値で裏付けられています。
6. 教育・啓発:社員のセキュリティ意識向上
技術的な対策と同じく重要なのが、社員のセキュリティ意識向上です。トレンドマイクロの調査によると、2024年の年間セキュリティインシデント公表件数は587件に達し、前年の1.5倍に増加しています。特に注目すべきは、全体の36.3%にあたる213件が「二次被害」(他組織で発生したサイバー攻撃による影響)だったという事実です。
これは、一つの組織がサイバー攻撃を受けると、委託先や取引先にも被害が波及する現代のビジネス環境を示しています。つまり、自社が完璧な対策を講じていても、取引先経由で被害を受けるリスクが高まっているということです。
最新のウイルス・詐欺手口、フィッシングメールの見分け方、安全なアプリ利用方法、インシデント発生時の対応について、定期的な教育を実施することで、こうした複雑化する脅威に対抗できる人材育成が不可欠です。統計上、人的要因によるセキュリティインシデントは全体の約8割を占めるため、技術的対策だけでなく、人への教育投資も欠かせません。
社用スマホセキュリティの定期点検
社用スマホのセキュリティレベルを維持するには、定期的な点検が欠かせません。以下のチェックポイントを確認しましょう。
基本設定の確認
- 画面ロックが適切に設定されているか
- 自動ロックが5分以内に設定されているか
- OSが最新バージョンに更新されているか
- 自動アップデートが有効になっているか
セキュリティソフトの状況
- 信頼できるウイルス対策アプリが導入済みか
- リアルタイムスキャンが有効になっているか
- 定期的なフルスキャンが実施されているか
- フィッシング対策機能がONになっているか
アプリ管理の状況
- 公式ストアからのみアプリをダウンロードしているか
- 不要なアプリを定期的に削除しているか
- アプリの権限設定が適切になっているか
- 業務用アプリとプライベートアプリが明確に分離されているか
通信・ネットワーク面の確認
- 主要サービスで2段階認証が設定されているか
- VPN利用体制が整備されているか
- 公衆Wi-Fi利用ルールが策定されているか
- 安全なネットワーク接続が確認されているか
データ管理の状況
- 重要データがクラウドに保存されているか
- 定期的なデータバックアップが行われているか
- 端末への機密情報保存が制限されているか
- データ暗号化設定が適切に行われているか

まとめ:社用スマホのウイルス対策は「経営リスク管理」そのもの
社用スマホのウイルス感染はもはや「ちょっとしたトラブル」ではありません。
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が10年連続でランサムウェアを情報セキュリティ脅威の第1位に選出している背景には、たった1台のスマートフォンから始まるサイバー攻撃が会社の信用失墜、事業停止、そして倒産リスクまで招く深刻な現実があります。
警視庁の最新統計では、ランサムウェア感染経路の86%がVPN機器やリモートデスクトップからの侵入となっており、特に中小企業が被害全体の64%を占めています。
そのため、「5つのウイルスに感染しています」のような偽警告に惑わされることなく、Android端末への脅威が2019年比で約2倍に増加している現実を踏まえた全端末のセキュリティ状況確認、VPN・リモートデスクトップ経由の感染が83%を占める統計を考慮したBYOD利用規程の策定、年間587件のセキュリティインシデント増加傾向に備えた緊急対応マニュアルの整備といった、本当に必要なセキュリティ対策を着実に実施することが重要です。
自社だけでは対策が難しい場合や、既にウイルス感染の疑いがある場合は、現状のセキュリティ診断、BYOD利用規程の作成支援、ウイルス感染時の緊急対応、従業員向けセキュリティ教育を提供する 株式会社テクノリレーションズまで、迷わずご相談ください。




