【小田原の中小企業向け】ホームページ運用が重要な理由|放置されたサイトの危険性と改善方法
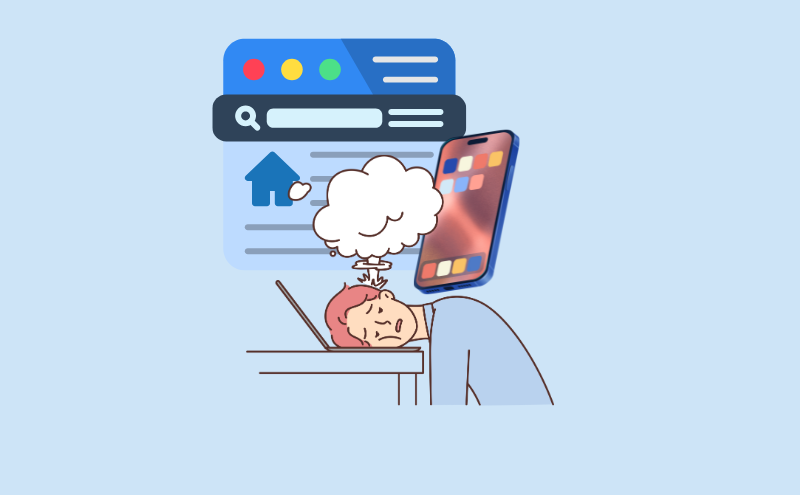
「数年前に高いお金を払ってホームページを作ったけど、その後ほとんど触っていない…」
小田原で事業を営む中小企業の経営者から、このような声をよく聞きます。実際に、ホームページを「作って終わり」にしてしまう企業は珍しくありません。しかし、この状況は想像以上に深刻な問題を引き起こしている可能性があります。
例えば、以下のような「あるある」に心当たりはありませんか?
- 営業時間が変わったのに、ホームページには古い情報が残っている
- 料金改定したのに、サイトには古い価格が掲載されている
- スタッフが退職したのに、まだ紹介ページに載っている
- 新商品やサービスを始めたのに、サイトに反映していない
- お客様から「ホームページの情報と違う」と指摘されたことがある
この記事では、なぜホームページの継続的な運用が重要なのか、放置することでどのようなリスクがあるのかを、 小田原の事業環境に即した具体例を交えて詳しく解説します。
放置されたホームページが引き起こす5つの深刻な問題
ホームページを放置することで生じる問題は、単に「情報が古い」だけでは済まされません。実際のビジネスに深刻な影響を与える可能性があります。
問題1顧客の信頼失墜と機会損失
最も深刻な問題は、顧客からの信頼を失うことです。現代の消費者は、事前にインターネットで情報を調べてから行動することが当たり前になっています。実際に、消費者の約8割が商品・サービスを利用する前にインターネットで情報収集を行っており、ホームページは「お店の顔」として重要な役割を果たしています。
具体的な例として、小田原の飲食店を考えてみましょう。お客様がランチタイムに来店しようとホームページで営業時間を確認したところ、「11:30~14:00」と記載されていました。しかし、実際には数ヶ月前から「12:00~14:30」に変更されており、11:45に到着したお客様は閉まっている店舗を見て困惑することになります。このような経験をしたお客様は、その店舗に対する信頼を失い、二度と利用しない可能性が高まります。
また、料金表が古いままの場合、お客様が予算を立てて来店したにも関わらず、実際の料金が高くなっていることで「だまされた」という印象を与えてしまいます。これは単なる情報の不一致を超えて、ビジネスの信頼性そのものを損なう深刻な問題です。
さらに、古い情報が原因で生じるクレームやトラブルは、スタッフの精神的負担にもなります。説明や謝罪に時間を取られることで、本来の業務に支障をきたし、結果的に他のお客様へのサービス品質も低下する悪循環が生まれます。
問題2検索エンジンでの評価低下
Googleなどの検索エンジンは、定期的に更新されるサイトを「活発で有用なサイト」として評価します。逆に、長期間更新されていないサイトは「古くて価値の低いサイト」と判断され、検索結果の順位が下がる傾向があります。
これは小田原という地域に限定したビジネスにとっても深刻な問題です。例えば、「小田原 美容院」「小田原 居酒屋」「小田原 整骨院」といったキーワードで検索された際に、競合他社が継続的にサイトを更新している中で、自社のサイトだけが放置されていると、どんどん検索順位が下がってしまいます。
実際に、定期的にブログ更新や新しい情報を発信している競合店舗が検索結果の上位に表示され、自社は2ページ目や3ページ目に追いやられてしまうケースは珍しくありません。検索結果の2ページ目以降をクリックする利用者は全体の1割程度というデータもあり、検索順位の低下は直接的な集客機会の損失につながります。
特に小田原のような地方都市では、インターネット検索による新規顧客の獲得が重要な集客手段となっているため、この影響は無視できません。観光客や移住者、近隣市町村からの来客など、地元の口コミだけではリーチできない潜在顧客を逃すリスクが高まります。
問題3競合他社との差別化の機会損失
ホームページの継続的な更新は、競合他社との差別化を図る重要な機会でもあります。新しいサービスの紹介、季節限定商品の案内、スタッフの専門性をアピールするコンテンツなど、更新を通じて自社の魅力を継続的に発信することで、競合他社に対する優位性を築くことができます。
例えば、小田原の税理士事務所の場合、税制改正の情報をタイムリーに発信したり、確定申告時期に合わせて役立つ情報を提供することで、専門性の高い事務所としての印象を与えることができます。一方、古い税制に基づく情報がそのまま掲載されているサイトは、専門家としての信頼性に疑問を持たれる可能性があります。
また、地域の特性を活かしたコンテンツ作りも重要です。小田原城周辺でのイベント情報、地元の食材を使った料理の紹介、小田原駅からのアクセス情報の詳細化など、地域密着型のビジネスならではの情報発信により、他の地域の競合とは異なる独自の価値を提供できます。
しかし、サイトが放置されていると、これらの差別化の機会を全て逃してしまいます。結果的に、価格競争に巻き込まれやすくなり、利益率の低下や顧客層の固定化といった問題を招く可能性があります。
問題4セキュリティリスクの増大
放置されたホームページは、セキュリティ面でも深刻なリスクを抱えています。IPA(情報処理推進機構)の「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」では、 中小企業1,117社に設置した機器が外部からの不審なアクセスを181,536件も検知したことが明らかになっています。また、個人情報保護委員会の発表によると、2023年度の個人情報漏えい件数は13,279件で過去最多となっており、そのうち86.3%がヒューマンエラーによるものでした。
実際に、放置されたWordPressサイトが乗っ取られ、違法サイトへのリダイレクトが仕込まれたり、フィッシング詐欺サイトとして悪用されたりする事例が後を絶ちません。このような状況になると、自社のサイトを訪問したお客様に迷惑をかけるだけでなく、Googleから「危険なサイト」として警告表示される可能性もあります。
小田原の中小企業にとって、このようなセキュリティインシデントは致命的な打撃となる可能性があります。地域コミュニティでの評判が重要なビジネス環境において、「あの会社のサイトはウイルスに感染している」という噂が広まれば、長年築いてきた信頼関係が一瞬で失われてしまいます。
また、個人情報保護法の観点からも、適切なセキュリティ対策を怠ることは法的リスクを伴います。2022年4月に施行された改正個人情報保護法では、 個人データの漏えい等が発生し個人の権利利益を害するおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化されました。顧客の連絡先情報や相談内容などが漏洩した場合、損害賠償責任を問われる可能性もあり、経済的な損失は計り知れません。
問題5スタッフのモチベーション低下
意外に見落とされがちですが、ホームページの放置は社内スタッフのモチベーションにも悪影響を与えます。古い情報が掲載されたまま放置されているサイトは、「会社が情報発信に力を入れていない」「デジタル化に消極的な会社」という印象を与え、特に若い世代のスタッフにとってはマイナスイメージとなります。
例えば、退職したスタッフの紹介がいつまでも掲載されていたり、数年前の古いサービス内容が残っていたりすると、現在働いているスタッフは「自分たちの取り組みが適切に評価・発信されていない」と感じる可能性があります。これは、スタッフの仕事に対する誇りや責任感の低下につながりかねません。
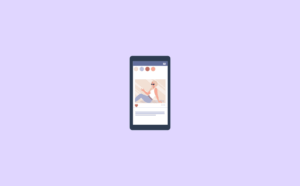
なぜホームページ運用が継続できないのか?よくある3つの原因
多くの小田原の中小企業がホームページ運用に苦戦する理由は、決して「やる気がない」からではありません。構造的な問題や環境的な制約が背景にあることがほとんどです。
原因1更新方法がわからない・引き継ぎ不足
最も多い問題は、「そもそも更新の仕方がわからない」ということです。ホームページ制作を外部業者に依頼した際、制作完了時の引き継ぎが不十分だったり、操作説明が専門的すぎて理解できなかったりするケースが頻発しています。
特に、WordPressなどのCMSを使用している場合、管理画面の操作方法、画像のアップロード方法、文字の編集方法など、基本的な操作でもIT知識がない人には難しく感じられます。制作業者からは「簡単に更新できます」と説明されても、実際に操作してみると思うようにいかず、結果的に触るのをやめてしまうパターンが多く見られます。
また、管理画面のログイン情報(ユーザー名やパスワード)を紛失してしまい、そもそもアクセスできなくなっているケースもあります。制作業者との契約が終了していたり、連絡が取れなくなっていたりすると、復旧に時間と費用がかかることになります。
さらに、更新作業に必要な画像の準備方法、適切なファイルサイズ、推奨される画像形式など、技術的な知識が必要な部分についての説明が不足していることも多く、「写真を追加したいけど、どうすればいいかわからない」という状況に陥りがちです。
WordPress(ワードプレス)とは、ホームページやブログを作成・管理するためのシステム(CMS:コンテンツ管理システム)です。世界中のウェブサイトの約40%がWordPressで作られており、小田原の多くの企業サイトでも利用されています。
原因2担当者の退職・人手不足
小田原の中小企業では、ホームページの管理を特定の一人に任せているケースが多く見られます。その担当者が退職や異動により不在になった際、後任者への引き継ぎが適切に行われず、更新作業が完全にストップしてしまう問題が頻発しています。
特に深刻なのは、比較的ITに詳しい若手社員にホームページ管理を任せていた場合です。その社員が転職や結婚などで退職すると、残されたスタッフは誰もホームページの操作方法を知らないという状況になります。小規模事業者では、一人の社員が複数の業務を兼任することが多いため、このような属人化のリスクが特に高くなります。
また、経営者自身がホームページ管理を行っていた場合、日常業務の忙しさから更新作業が後回しになり、気づけば数ヶ月、場合によっては数年間も放置されているケースもあります。小田原で事業を営む経営者は、営業活動、経理処理、人材管理など多岐にわたる業務を同時にこなす必要があり、ホームページ更新の優先順位が相対的に低くなりがちです。
さらに、人手不足の問題は、新たな担当者の育成にも影響します。ホームページ運用のスキルを身につけるには一定の時間と学習コストが必要ですが、日々の業務に追われる現場では、そのような教育時間を確保することが困難です。結果的に、「重要だとはわかっているが、手をつけられない」という状況が続くことになります。
原因3コスト意識と投資対効果への疑問
IPA「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」によると、 情報セキュリティ対策投資を行わなかった理由として「必要性を感じていない」が44.3%で最も多く、「費用対効果が見えない(24.2%)」、「コストがかかりすぎる(21.7%)」が続いています。中小企業として資金が限られる中で情報セキュリティ投資に踏み出せない状況が伺えます。
小田原という地域特性もこの問題に影響しています。従来の地域密着型ビジネスでは、口コミや紹介による集客が主流だったため、デジタルマーケティングの効果を実感しにくい環境があります。「昔からのお客様がいるから、ホームページがなくても大丈夫」という考え方が根強く、インターネット経由の集客効果を軽視してしまう傾向があります。
また、ホームページの効果測定が適切に行われていないことも問題です。アクセス解析ツールの設定がされていない、問い合わせの経路が追跡できていない、などの理由で、ホームページからの集客効果が見えにくくなっています。効果が数値化されていないため、「お金をかけても意味がない」という結論に至ってしまうのです。
さらに、更新作業を外部に依頼する場合の費用体系についての理解不足も影響しています。「文章を少し変更するだけで数万円かかる」という誤解や、「毎月高額な保守費用を支払わなければならない」という思い込みにより、更新自体を諦めてしまうケースもあります。実際には、基本的な更新作業であれば比較的低コストで対応可能ですが、そのような情報が適切に伝わっていないことが問題となっています。

継続的なホームページ運用がもたらす5つのメリット
ホームページを継続的に運用することで得られるメリットは、単に「情報が新しくなる」だけではありません。ビジネス全体に波及する様々な効果が期待できます。
メリット1:検索エンジンでの上位表示と集客力向上
継続的な更新により、検索エンジンでの評価が向上し、より多くの潜在顧客にリーチできるようになります。特に小田原という地域キーワードと組み合わせた検索において、上位表示される可能性が大幅に高まります。一般的に、検索結果の1位表示で約30%、3位でも約15%のクリック率が期待できるとされています。
具体的な効果として、「小田原 + 業種名」での検索結果で1ページ目に表示されることで、月間数百人から数千人の新規訪問者を獲得できる可能性があります。例えば、「小田原 歯医者」というキーワードで月間1,000回検索されている場合、1位に表示されれば約300人、3位でも約150人のクリックが期待できます。
また、ブログ記事などのコンテンツを定期的に追加することで、より多様なキーワードでの検索流入が見込めます。「小田原 虫歯 痛み」「小田原 歯科 予防」「小田原 インプラント 費用」など、具体的な悩みや目的を持った検索ユーザーにリーチできるようになり、質の高い見込み客の獲得につながります。
さらに、Googleマイビジネスとの連携により、地図検索での表示機会も増加します。小田原駅周辺での検索や、「近くの○○」といった位置情報を活用した検索において、適切に表示されることで、通りがかりの顧客や観光客の来店促進効果も期待できます。
メリット2:顧客との信頼関係構築
定期的な情報発信は、顧客との継続的なコミュニケーションツールとしても機能します。新しいサービスの案内、スタッフの紹介、業界トレンドの解説など、価値のある情報を提供することで、単なる取引関係を超えた信頼関係を構築できます。
例えば、小田原の工務店が季節ごとの住宅メンテナンス情報を発信したり、地域の気候特性に合わせた建築アドバイスを提供したりすることで、「この会社は地域の特性を理解している専門家」という印象を与えることができます。このような継続的な価値提供により、顧客の中で「困ったときはこの会社に相談しよう」という位置づけを獲得できます。
また、透明性の高い情報発信も信頼構築に重要です。料金体系の明確化、施工事例の詳細な紹介、スタッフの資格や経験の開示など、オープンで誠実な情報提供により、顧客の不安を解消し、安心感を与えることができます。
さらに、お客様の声や実際の事例を紹介することで、社会的証明の効果も期待できます。小田原の地域コミュニティにおいて、実在する顧客からの推薦や感謝の声は、新規顧客にとって非常に説得力のある情報となります。
メリット3:競合他社との差別化
継続的な情報発信により、自社の専門性や独自性をアピールし、競合他社との明確な差別化を図ることができます。特に小田原のような地域密着型ビジネスにおいて、地域への理解と貢献をアピールすることは重要な差別化要素となります。
例えば、地域のイベント参加報告、小田原の歴史や文化に関連したコンテンツ、地元食材を使った商品開発の背景など、地域密着企業ならではの情報発信により、単なる価格競争を避けて付加価値の高いポジションを確立できます。
また、業界の最新トレンドや技術情報を継続的に発信することで、「常に勉強している」「新しい知識を取り入れている」という印象を与え、プロフェッショナルとしての信頼性を高めることができます。これは特に専門性が重要な業種(医療、法務、建築、ITなど)において効果的です。
さらに、自社の取り組みや理念を継続的に発信することで、価値観を共有できる顧客との長期的な関係構築が可能になります。単純な価格比較ではなく、「この会社の考え方に共感する」「この会社と一緒に仕事をしたい」という感情的なつながりを築くことで、より安定した顧客基盤を形成できます。
メリット4:新規事業や商品の効果的な告知
ホームページが継続的に運用されていることで、新しいサービスや商品を効果的に告知するプラットフォームとして活用できます。従来の新聞折込チラシやDMと比較して、より詳細な情報を低コストで発信できる利点があります。
特に小田原という地域において、地域限定のサービスや季節商品の告知は重要な集客手段となります。例えば、梅の季節に合わせた特別メニュー、小田原城のイベントに連動したキャンペーン、地域の祭りに合わせたサービス提供など、タイムリーな情報発信により効果的なプロモーションが可能になります。
また、新規事業の立ち上げ時には、既存顧客への告知ツールとしても活用できます。すでにホームページを訪問する習慣がある顧客に対して、新しい取り組みを効率的に知らせることで、初期の顧客獲得を円滑に進めることができます。
さらに、新商品やサービスの開発プロセスを公開することで、顧客との協創関係を築くことも可能です。「お客様の声を受けて新しいサービスを検討中」「試作品のご意見をお聞かせください」といった参加型のコンテンツにより、顧客エンゲージメントを高めることができます。
メリット5:採用活動での企業魅力アピール
継続的に更新されるホームページは、優秀な人材を採用するためのツールとしても重要な役割を果たします。求職者の多くは応募前に企業のホームページを詳しく調べるため、そこで得られる印象が採用成功に大きく影響します。
小田原の人材市場において、地域の魅力と会社の特徴を組み合わせたアピールは効果的です。「小田原という住みやすい環境で、やりがいのある仕事ができる」「地域に貢献できる会社で働ける」といったメッセージを、具体的な事例とともに発信することで、価値観を共有できる人材の応募を促進できます。
また、実際の職場環境や働いているスタッフの様子を紹介することで、求職者の不安を解消し、安心して応募できる環境を提供できます。特に中小企業の場合、大企業と比較して知名度や安定性に不安を感じる求職者も多いため、職場の雰囲気や成長機会を具体的に示すことが重要です。
さらに、社員の成長事例やキャリアパスを紹介することで、「この会社で働くことで自分も成長できる」という期待感を醸成できます。研修制度の充実、資格取得支援、昇進の実例など、人材育成への取り組みを継続的に発信することで、向上心の高い人材の獲得につながります。
今すぐ始められる!基本的なホームページ運用方法
ホームページ運用の重要性は理解できても、「何から始めればいいかわからない」という方も多いでしょう。ここでは、IT知識がない方でも今日から実践できる基本的な運用方法を具体的に解説します。
ステップ1現在の状況を確認する
まずは、現在のホームページの状態を客観的に把握することから始めましょう。以下のチェック項目を確認してください:
- 基本情報の確認:営業時間、定休日、料金、連絡先などが最新の情報になっているか
- スタッフ情報:現在働いているスタッフの情報が正確に掲載されているか
- サービス内容:現在提供しているサービスと一致しているか
- 写真や画像:現在の店舗や商品の状況を反映しているか
- お知らせ欄:最後に更新された日付はいつか
この確認作業により、どの部分を優先的に更新すべきかが明確になります。特に、お客様が最初に確認する可能性が高い営業時間や料金などの基本情報は、最優先で修正しましょう。
また、Googleマイビジネスの情報との整合性も重要です。ホームページとGoogleマイビジネスで異なる情報が掲載されていると、お客様が混乱する原因となります。両方のプラットフォームで一貫した情報を提供することを心がけてください。
ステップ2更新頻度とスケジュールを決める
継続的な運用を成功させるためには、無理のない更新スケジュールを設定することが重要です。最初から高い頻度を目標にすると挫折しやすいため、まずは月1回程度の更新から始めることをお勧めします。
効果的な更新スケジュールの例:
- 毎月第1営業日:基本情報(営業時間、料金等)の確認と必要に応じた修正
- 毎月第3営業日:新しいお知らせやブログ記事の投稿
- 季節の変わり目:写真の差し替えや季節限定サービスの追加
- 年2回:全体的なコンテンツの見直しと大幅な更新
重要なのは、決めたスケジュールを確実に実行することです。そのためには、更新作業を担当者の個人的な判断に委ねるのではなく、会社の業務の一部として位置づけ、時間を確保することが必要です。
また、緊急時の更新体制も準備しておきましょう。台風や雪などの天候不良による臨時休業、システムトラブルによるサービス停止など、急な変更を迅速に告知できる体制を整えておくことで、お客様への影響を最小限に抑えることができます。
ステップ3簡単な更新から始める
ホームページ運用の習慣を身につけるために、まずは簡単な更新作業から始めましょう。技術的な知識がなくても対応できる基本的な更新項目は以下の通りです:
文字情報の更新:
- 営業時間や定休日の変更
- 料金の改定
- 電話番号やメールアドレスの変更
- お知らせやニュースの追加
- 簡単な挨拶文やメッセージの更新
写真の差し替え:
- 季節に合わせた店舗外観の写真
- 新商品やメニューの写真
- スタッフの写真(新入社員の紹介など)
- イベントや活動の様子
写真を更新する際は、画質やサイズに注意が必要です。高画質すぎる写真はページの読み込み速度を遅くする原因となるため、適切なサイズに調整してから使用しましょう。多くのスマートフォンやデジタルカメラで撮影した写真は、そのままではファイルサイズが大きすぎることがあります。
また、写真を撮影する際は、清潔感のある明るい写真を心がけてください。特に飲食店や美容院などのサービス業では、写真の印象が来店意欲に直結するため、照明や構図にも配慮することが重要です。
ステップ4お客様の声を活用する
継続的なコンテンツ作成において、最も効果的で取り組みやすい方法の一つが「お客様の声」の活用です。実際の顧客からのフィードバックや感謝の言葉は、新規顧客にとって非常に説得力のある情報となります。
お客様の声を効果的に活用するポイント:
- 許可を得る:掲載前に必ずお客様の承諾を得る
- 具体性を重視:「良かった」だけでなく、何がどのように良かったかを具体的に記載
- 写真も合わせて:可能であれば、お客様との記念写真や施工事例写真も掲載
- 多様性を意識:年齢層や利用目的の異なる様々なお客様の声を紹介
- 定期的な更新:古い声だけでなく、最新の声も継続的に追加
特に小田原という地域においては、地元の方からの声は大きな影響力を持ちます。「小田原在住の○○さん」「地元で長年お世話になっています」といった地域密着感のあるコメントは、同じ地域の住民にとって親近感と信頼感を与える重要な要素となります。
また、お客様の声を収集する仕組みも重要です。アンケート用紙の設置、メールでのフォローアップ、SNSでの感想募集など、様々な方法でお客様の率直な意見を集めることで、継続的なコンテンツ作成の材料を確保できます。
ステップ5地域情報との連携
小田原の事業者にとって、地域情報との連携は効果的な差別化戦略となります。地域のイベント、季節の話題、観光情報などと自社のサービスを関連付けることで、地域密着企業としてのアイデンティティを強化できます。
具体的な連携方法:
- 季節イベントとの連動:梅まつり、花火大会、お城まつりなどの期間中の特別サービス案内
- 観光客向け情報:小田原城からのアクセス方法、観光ついでに利用できるサービスの紹介
- 地域の話題への反応:新しい商業施設の開業、交通機関の変更などに関する情報提供
- 地域貢献活動:地域清掃活動への参加、地元イベントへの協賛などの報告
このような地域密着型のコンテンツは、SEO効果も期待できます。「小田原 + 関連キーワード」での検索において、地域情報を含むページは検索エンジンから高く評価される傾向があります。また、地域住民や観光客が情報収集する際の有用なリソースとして認識されることで、自然なリンク獲得や口コミ拡散の効果も期待できます。
外部サポートの効果的な活用方法
ホームページ運用の重要性は理解できても、社内だけでは十分な対応が困難な場合もあります。そのような時は、外部の専門家やサービスを効果的に活用することで、継続的な運用を実現できます。
どんな場合に外部サポートを検討すべきか
以下のような状況に該当する場合は、外部サポートの活用を積極的に検討することをお勧めします:
- 技術的な問題:システムエラー、表示不具合、セキュリティ問題などが発生している
- 時間的制約:日々の業務が忙しく、定期的な更新時間を確保できない
- 専門知識の不足:SEO対策、アクセス解析、コンテンツマーケティングなどの専門領域
- 大幅な改修の必要性:デザインの刷新、機能追加、スマートフォン対応などの大規模な変更
- 効果測定の必要性:ホームページからの集客効果を数値化して把握したい
特に小田原の中小企業では、限られた人員で多様な業務をこなす必要があるため、専門性の高い作業については外部の力を借りることが現実的な解決策となります。
外部サポートを選ぶ際のポイント
ホームページ運用のサポートを依頼する際は、以下の点を確認することが重要です:
- 地域への理解:小田原の地域特性やビジネス環境を理解している
- コミュニケーション:専門用語を使わず、わかりやすく説明してくれる
- 料金体系の透明性:作業内容と費用の関係が明確になっている
- 実績と信頼性:類似業種での実績があり、長期的な関係構築が可能
- 緊急時の対応:トラブル発生時に迅速に対応してくれる体制がある
また、全てを外部に依存するのではなく、社内でできることと外部に委託することを明確に分けることも重要です。基本的な情報更新は社内で行い、技術的な問題や専門的な施策は外部に依頼するといった役割分担により、コストを抑えながら効果的な運用が可能になります。
まとめ:継続的なホームページ運用で小田原での事業成長を実現
ホームページの放置は信頼失墜や集客機会損失を招く深刻なリスクです。一方、継続的な運用により検索上位表示、顧客信頼獲得、競合差別化が実現できます。小田原の中小企業には、まず現状確認から始めて月1回の簡単な更新を習慣化することをお勧めします。完璧を目指さず継続を優先し、必要に応じて外部サポートを活用することで、地域に根ざした持続可能な事業成長が可能になります。
ホームページ運用に関する具体的な支援や、貴社の状況に応じたカスタマイズされたアドバイスが必要な場合は、株式会社テクノリレーションズまでお気軽にお問い合わせください。小田原の事業者様の成功を全力でサポートいたします。




