目次
「電子カルテを導入したけれど、セキュリティは本当に大丈夫なのか?」、「うちは小さなクリニックだから狙われないだろうと思っていたが、最近ニュースでサイバー攻撃の話をよく聞くし、心配になってきた…」
このような不安を抱えているクリニックの院長先生は決して少なくありません。実際に、患者さんから「先生のところは大丈夫ですか?」と直接質問されたことがある院長もいらっしゃるのではないでしょうか。
最近のニュースでも、医療機関がサイバー攻撃を受けて患者情報が流出したり、電子カルテが使えなくなって診療に支障が出る事例が相次いで報告されています。特に小規模なクリニックや診療所では、「ITの専門知識がないから何をすればいいかわからない」「費用をかけずに対策したい」という声を多く聞きます。
この記事では、ITが苦手な院長先生でも今日から実践できる、基本的で効果的なセキュリティ対策を5つに絞ってご紹介します。難しい専門用語は使わず、「なぜその対策が必要なのか」「具体的にどうすればいいのか」をわかりやすく解説していきます。
なぜ医療機関がサイバー攻撃の標的になるのか?最新データで見る現状
まずは現状を数字で確認してみましょう。警察庁の発表によると、医療・福祉分野におけるランサムウェア(身代金要求型ウイルス)の被害件数は、近年増加傾向にあることが報告されています。
特に深刻なのは、一度攻撃を受けると被害が甚大になりやすいことです。厚生労働省の報告書では、サイバー攻撃により電子カルテが使用できなくなった医療機関が、通常業務に戻るまでに数ヶ月を要したケースが複数確認されています。
実際に起きている被害事例
近年、以下のような深刻な事例が相次いで発生しています。
- 地方の精神科医療機関で数万人規模の患者情報が流出
- 総合病院で電子カルテシステムが暗号化され、数ヶ月間の復旧期間を要した
これらの事例に共通するのは、「まさか自分のところが攻撃されるとは思わなかった」という医療機関側の認識です。攻撃者は規模の大小に関係なく、対策が不十分な医療機関を狙っています。
なぜクリニックが狙われやすいのか?
医療機関、特に小規模なクリニックが攻撃の標的になりやすい理由は以下の4つです:
価値の高い個人情報を扱っている
患者さんの氏名、住所、病歴、保険証番号など、悪用価値の高い情報が大量に保存されている
社会的責任の重さ
診療を止めるわけにいかないため、身代金の要求に応じやすいと攻撃者が考えている
セキュリティ対策の遅れ
IT専門スタッフがおらず、基本的な対策も不十分な医療機関が多い
ネットワークの複雑さ
電子カルテ、医療機器、レセプトシステムなど複数のシステムが連携しており、どこか一箇所でも突破されると全体に影響が及ぶ
「うちは小さいから大丈夫」ではなく、むしろ「小さいからこそ対策が必要」なのが現実です。
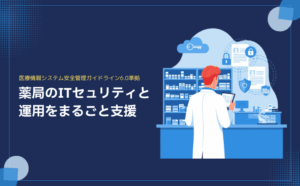
小田原の医療ITサポート|クリニック・薬局のガイドライン6.0・ISO27001対応
小田原の医療機関向けITサポート。クリニック・薬局のセキュリティ対策や監査対応を、ガイドライン6.0準拠・ISO27001取得の体制で支援します。
厚生労働省も推奨!院長が今すぐできるセキュリティ対策5選
厚生労働省が公表した「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」では、医療機関が最低限実施すべき対策が明確に示されています。この中から、特にクリニックの院長先生が今日から実践できる対策を5つ厳選しました。
対策1:パスワードの見直しと強化
最も基本的でありながら、最も効果的な対策がパスワードの強化です。厚生労働省の調査では、サイバー攻撃を受けた医療機関の多くで「推測しやすいパスワード」や「複数のシステムで同じパスワードの使い回し」が確認されています。
多くのクリニックで見られる危険なパスワードの例:
- 「password123」「admin」といった初期設定のまま
- クリニック名や院長名をそのまま使用
- 電子カルテ、レセプトシステム、ルーターなど全てで同じパスワード
- スタッフ全員が同じパスワードを共有
これらは攻撃者にとって「鍵をかけていない金庫」のようなものです。今すぐ以下の方法で改善しましょう:
すぐにできるパスワード強化法
- 長さは13文字以上:「ClinicSafety2025!」のように、意味のある文字と数字・記号を組み合わせる
- システムごとに異なるパスワード:電子カルテ、レセプト、ルーターなど、全て別々のパスワードを設定
- 定期的な変更:最低でも3ヶ月に1回は変更する
- スタッフ個別のアカウント:共有アカウントは廃止し、スタッフごとに個別のアカウントを作成
パスワードセキュリティの詳細については、以下もご参考ください。

たった3分で会社を守る!忙しい経営者のためのIT見直しチェックリスト
「時間がない」経営者必見。ITの“見直しどころ”を3分でチェックできるリストを用意しました。セキュリティ、データ管理、コストまで今すぐ確認できます。
対策2:スタッフへの基本的なセキュリティ教育
多くのサイバー攻撃は「メール」が入り口となっています。実際に、フィッシングメールや添付ファイルを通じた侵入が最も多い攻撃手法として報告されています。どれだけ技術的な対策を講じても、スタッフが怪しいメールを開いてしまえば簡単に侵入されてしまいます。
実際にクリニックに送られてくる危険なメールの例:
- 「緊急:電子カルテシステムの更新が必要です」といった偽の案内
- 「患者さんからの苦情です。添付ファイルをご確認ください」
- 「保険関連の重要なお知らせ」として送られる偽メール
- 「システム管理会社」を名乗る偽のサポートメール
これらのメールは見た目が非常に本物に近く、忙しい業務の中では見分けが困難です。だからこそ、スタッフ全員が基本的な知識を持つことが重要です。
毎月5分でできるセキュリティミーティング
月に1回、朝礼や終礼の時間を5分延長して、以下の内容を確認しましょう:
- 今月の注意事項:「添付ファイルは必ず確認してから開く」など、1つのポイントに絞って確認
- 疑問の共有:「こんなメールが来たけど大丈夫?」といった疑問をスタッフ間で共有
- 対応方法の確認:「怪しいと思ったら院長に相談」など、シンプルなルールを徹底
完璧を求める必要はありません。「疑わしいものは一旦立ち止まって確認する」という習慣を作ることが最も重要です。
対策3:USBメモリ・外部機器の利用制限
USBメモリは便利な一方で、ウイルス感染の大きな原因となります。厚生労働省のガイドラインでも「USB等の外部記録媒体の接続制限」が重要な対策として位置づけられています。
クリニックでよくある危険なUSB利用例:
- 学会発表用の資料を自宅のパソコンで作成し、USBで持参
- 患者さんから「写真をUSBで持参したので診察時に見てほしい」と言われて接続
- 医療機器メーカーの営業担当が「新しいソフトをUSBでお持ちしました」
- スタッフが私用のUSBを業務用パソコンに接続
これらはすべて感染リスクの高い行為です。以下のルールを院内で徹底しましょう:
USB利用の安全ルール
- 原則として私用USBの業務利用禁止:業務に必要な場合は、クリニック専用のUSBのみ使用
- 外部からのUSB接続は事前確認:患者さんや業者からUSB利用の依頼があった場合は、一旦お預かりしてウイルスチェックを実施
- 重要データの外部持ち出し禁止:学会発表等でデータが必要な場合は、クラウドサービスの利用を検討
- 持ち出し管理簿の作成:やむを得ずUSBを使用する場合は、使用者・使用目的・期間を記録
「面倒くさい」と思われるかもしれませんが、一度の感染で失うものを考えれば、この程度の手間は十分に価値があります。
対策4:定期的なシステム更新(アップデート)の実施
多くのサイバー攻撃は、ソフトウェアの「脆弱性(セキュリティの穴)」を突いて行われます。この脆弱性は、定期的なアップデートによって修正されるため、更新を怠ることは「玄関の鍵を開けっ放しにしている」のと同じです。
クリニックで特に注意すべきシステム:
- 電子カルテシステム:メーカーからの更新案内は必ず確認
- レセプトシステム:社会保険関連の改正に合わせて頻繁に更新が必要
- ルーター・ネットワーク機器:購入時から一度も更新していないケースが多い
- ウイルス対策ソフト:定義ファイルの自動更新設定を確認
- Windows・Mac等の基本OS:自動更新の設定を有効にする
更新作業で気をつけるポイント
- 診療時間外に実施:患者さんに迷惑をかけないよう、休診日や診療終了後に実施
- バックアップの確認:更新前に必ずデータのバックアップが取れていることを確認
- 業者との連携:電子カルテ等の重要システムは、必ず業者と相談してから更新
- 更新記録の保管:いつ、何を、誰が更新したかを記録として残す
「更新で不具合が起きたら困る」という不安もあるでしょうが、更新しないリスクの方がはるかに高いのが現実です。適切な手順で実施すれば、問題が起きることはまれです。
対策5:バックアップ体制の確立
万が一サイバー攻撃を受けてしまっても、適切なバックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。厚生労働省のガイドラインでも「オフライン・バックアップ体制の整備」が強く推奨されています。
多くのクリニックで見られるバックアップの問題:
- バックアップを取っているつもりだが、実際には同じネットワーク内に保存しているため、攻撃時に一緒に暗号化されてしまう
- バックアップは取っているが、復元の手順を確認したことがない
- 重要なデータの一部しかバックアップしていない
- バックアップの頻度が不定期で、最新データが保護されていない
効果的なバックアップの「3-2-1ルール」
プロが推奨するバックアップの基本ルールです:
- 3つのコピー:元データ + バックアップ2つの合計3つのコピーを保持
- 2つの異なる媒体:ハードディスクとクラウドなど、異なる種類の媒体に保存
- 1つはオフライン:ネットワークから切り離した場所に1つは保管
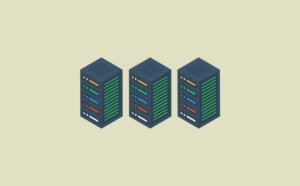
中小企業が今こそ取り組むべきIT資産管理|なぜ必要なのか徹底解説
IT資産管理は中小企業にとって不可欠な時代。セキュリティ、コスト削減、業務効率化を実現するための重要性と、資産数増加時に検討すべきソリューション導入についても詳しく解説します。
クリニック向けの具体的なバックアップ例:
- 毎日:電子カルテの自動バックアップ(システム内蔵機能を利用)
- 毎週:外付けハードディスクへの完全バックアップ
- 毎月:クラウドサービスへの重要データバックアップ
- 四半期ごと:バックアップからの復元テストを実施
バックアップは「保険」と同じです。使わずに済めばそれが一番ですが、いざという時に役立たなければ意味がありません。定期的な復元テストも忘れずに実施しましょう。
緊急時の対応手順を準備しておく
どれだけ対策を講じても、サイバー攻撃のリスクを完全にゼロにすることはできません。重要なのは、万が一の際に迅速かつ適切に対応できる体制を整えておくことです。
サイバー攻撃を受けた時の初動対応
攻撃を受けた、または受けた疑いがある場合の対応手順を事前に決めておきましょう:
- システムの切り離し:被害の拡大を防ぐため、該当するコンピューターをネットワークから切り離す
- 現状の記録:画面の写真撮影、エラーメッセージの保存など、証拠となる情報を記録
- 関係者への連絡
- 業務継続の検討:紙カルテでの診療継続、患者さんへの状況説明など
- 復旧計画の策定:専門業者と連携した復旧スケジュールの確認
重要なのは、パニックにならずに冷静に対応することです。事前に連絡先をまとめた「緊急連絡リスト」を作成し、スタッフ全員が見える場所に掲示しておきましょう。
【重要】厚生労働省ガイドラインの複雑さと、専門業者サポートの必要性
ここまで、院長先生が今すぐできる基本的なセキュリティ対策をご紹介してきました。しかし、正直にお伝えすると、これらは「最低限の対策」に過ぎません。
実は、医療機関には厚生労働省が策定した 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」の遵守が求められており、その内容は想像以上に複雑で専門的なものです。
ガイドライン第6.0版の構成と複雑さ
最新のガイドライン第6.0版は、以下の4編で構成されており、全体で数百ページにわたる膨大な資料となっています:
- 概説編:全体の考え方や前提知識
- 経営管理編:院長などの経営層が理解すべき事項
- 企画管理編:システム管理者向けの技術的要件
- システム運用編:日常的な運用管理の詳細手順
これらの中には、以下のような高度で専門的な対策が含まれています:
技術的要件の例
- ゼロトラストネットワークの構築:従来の境界防御に加えて、内部ネットワークでも全てのアクセスを検証する仕組み
- 2要素認証の実装:重要なシステムでは「知識」「生体」「物理媒体」のうち2つ以上を組み合わせた認証の導入が推奨
- ネットワークセグメンテーション:電子カルテ、医療機器、一般業務システムを適切に分離
- ログ管理と監視体制:全システムのアクセス記録を取得し、異常な動作を検知する仕組み
- 事業継続計画(BCP)の策定:サイバー攻撃を想定した診療継続計画
立入検査でのチェック項目
さらに、2023年6月からは都道府県による立入検査において、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」に基づく確認が実施されています。このチェックリストには多数の詳細な確認事項が含まれており、以下のような項目が確認されます:
- パスワードポリシーの文書化と遵守状況
- USB接続制限の技術的実装状況
- ネットワーク機器の脆弱性管理体制
- バックアップデータの暗号化と世代管理
- インシデント対応手順書の策定と訓練実施状況
- 委託業者との責任分界点の明確化
- 医療機器のセキュリティパッチ適用状況
なぜ専門業者のサポートが必要なのか
これらの要件を見ていただければお分かりの通り、 医療の専門家である院長先生が片手間で対応できる内容ではありません。実際に、以下のような理由から多くの医療機関で対応に苦慮しているのが現状です:
- 専門知識の不足:ネットワークセキュリティやシステム構築には、ITの専門知識が不可欠
- 時間的制約:日々の診療業務に加えて、膨大なガイドラインを理解し実装する時間的余裕がない
- 継続的な管理が必要:一度設定すれば終わりではなく、定期的な更新や監視が必要
- 法令対応の複雑さ:医療法、個人情報保護法、サイバーセキュリティ基本法など複数の法令への対応が必要
- 責任の重さ:設定ミスや対応漏れが重大なセキュリティ事故につながるリスク
適切な業者選びのポイント
では、どのような業者に相談すべきでしょうか。医療機関のITセキュリティ対策を依頼する際の重要なポイントをご紹介します:
必須条件
- 医療機関での実績:医療業界特有の要件や法令を理解している
- ガイドライン準拠:厚生労働省ガイドライン第6.0版に対応できる
- 継続的な管理:一度の設定だけでなく、継続的な監視・更新に対応
- 明確な責任分界:何をどこまで対応してくれるかが明確
信頼できる業者なら、現状の診断から対策の実装、継続的な運用サポートまで、トータルでサポートしてくれます。「餅は餅屋」という言葉通り、医療の専門家である院長先生は診療に専念し、ITセキュリティは専門業者に任せるのが最も効率的で安全な方法です。
まとめ:患者さんの安心のために、段階的なセキュリティ強化を
医療機関を取り巻くサイバーセキュリティの脅威は日々高まっており、「うちは小さいから大丈夫」という考えは通用しなくなっています。患者さんの大切な個人情報と、地域医療を守るためには、適切なセキュリティ対策が不可欠です。
まずは今回ご紹介した基本的な対策から始めて、段階的にセキュリティレベルを向上させていくことが重要です。そして、本格的なガイドライン対応や高度なセキュリティ対策については、医療機関専門のITサポート業者への相談を強くおすすめします。
患者さんから「先生のところは安心ですね」と言っていただけるような医療機関のITサポートに精通した専門業者と連携して、確実なセキュリティ体制を構築していきましょう。
セキュリティ対策は「投資」です。事故が起きてからでは遅すぎます。今こそ行動を起こし、患者さんと地域医療を守るための体制を整える時です。

