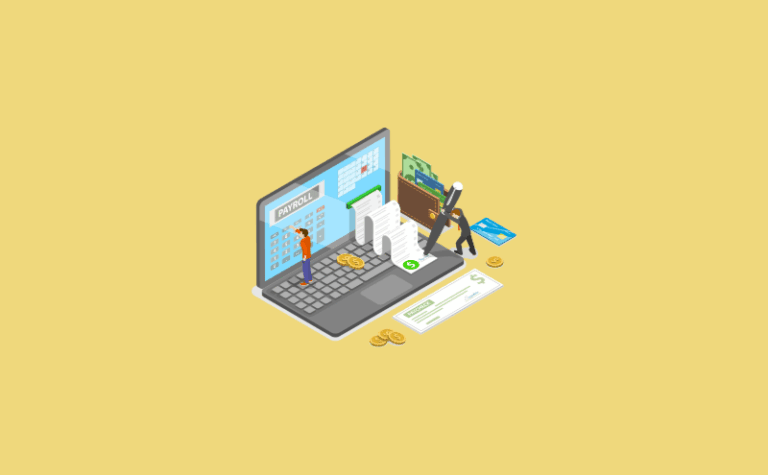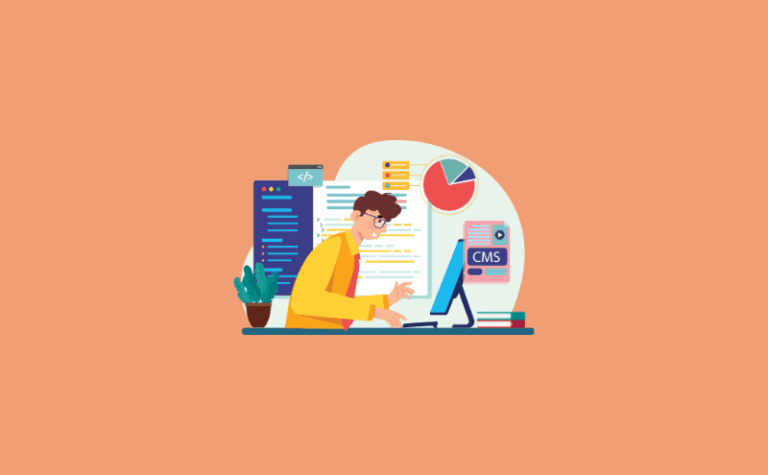目次
USBメモリは軽くて持ち運びも便利。社外での作業やデータの受け渡しに、長年使われてきたツールです。
しかしその“手軽さ”が、今では情報漏洩のリスクになっていることをご存じでしょうか?
この記事では、USBメモリの持ち出しが抱える問題点と、今すぐ見直すべき「情報持ち出しルール」について解説します。
ITに詳しくない中小企業の経営者や、ひとり情シスのIT担当者にもわかりやすいようにまとめました。
USBメモリの“便利さ”が、会社を危険にさらす
USBメモリは便利ですが、企業のセキュリティポリシーとしては「時代遅れ」のツールになりつつあります。
万が一紛失した場合、データが暗号化されていなければ、中に保存されているファイルは誰でも閲覧できてしまいます。
持ち出された情報が外部に流出すれば、顧客との信頼関係が損なわれ、賠償責任や取引停止といった深刻な事態にもなりかねません。
USBメモリによる情報漏洩、実際に起きている
中小企業でも、以下のようなトラブルが実際に報告されています。
- 営業担当が顧客リストをUSBで持ち出し、カフェで紛失
- 退職する社員が、社内資料をUSBにコピーして持ち出し
- 安価なUSBメモリがウイルスに感染しており、社内ネットワークに被害
こうした事例は大企業に限らず、中小企業にも十分起こり得ます。
今すぐ見直すべき!情報持ち出しルール5選
情報漏洩を防ぐためには、「何を、誰が、どのように」扱うかというルールを明文化しておくことが重要です。以下は最低限押さえておきたいルールです。
1. USBメモリの使用を原則禁止にする
基本的にはUSBメモリの利用は不可とし、どうしても必要な場合は事前申請・承認制とすることで管理できます。
2. 機密データはクラウドで共有・管理する
GoogleドライブやOneDriveなどのクラウドを使うことで、物理的な持ち出しを回避できます。アクセス権限の設定も柔軟です。
3. 暗号化とパスワード保護を徹底する
やむを得ずUSBを使う場合は、必ずデータを暗号化し、ファイルやUSB自体にパスワードを設定します。
4. 外部デバイスの接続制限を設定する
WindowsのポリシーやMDM(モバイルデバイス管理)ツールで、USBデバイスの使用制限が可能です。
5. 社員の教育と意識づけ
ルールを作っても守られなければ意味がありません。情報漏洩のリスクを伝え、定期的な研修や注意喚起を行いましょう。
社内ルールを浸透させる3つのポイント
ルールを形だけ整えても、実際の現場で機能しなければ意味がありません。以下のような工夫が効果的です。
- シンプルでわかりやすいルールにする
- 紙だけでなく、掲示板やチャットでも周知する
- 違反があったときの対応ルールも用意する
ルール作成が難しい場合は、ITサポートの活用を
セキュリティポリシーや運用ルールの策定は、ITに不慣れな企業にはハードルが高いものです。
株式会社テクノリレーションズでは、中小企業に特化した情報セキュリティ支援を行っています。
- 社内の現状調査とリスク洗い出し
- ルールの策定・社内教育資料の作成
- クラウド移行やMDM導入支援
「どこから手をつけてよいかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。
まとめ|情報管理の第一歩は“持ち出しルール”から
USBメモリの持ち出しは、便利である一方、情報漏洩のリスクと隣り合わせです。
中小企業こそ、明確なルールと運用体制を整えることで、大きなリスクを未然に防ぐことができます。
これを機に、自社の情報管理ルールを見直してみませんか?
株式会社テクノリレーションズでは、セキュリティポリシーの策定から運用までワンストップで支援しています。ルール作りに悩んでいる方は、ぜひ一度お問い合わせください。