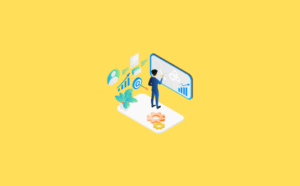その”油断”が命取り!小田原・箱根の中小企業のための”やさしい社内セキュリティ教育”入門
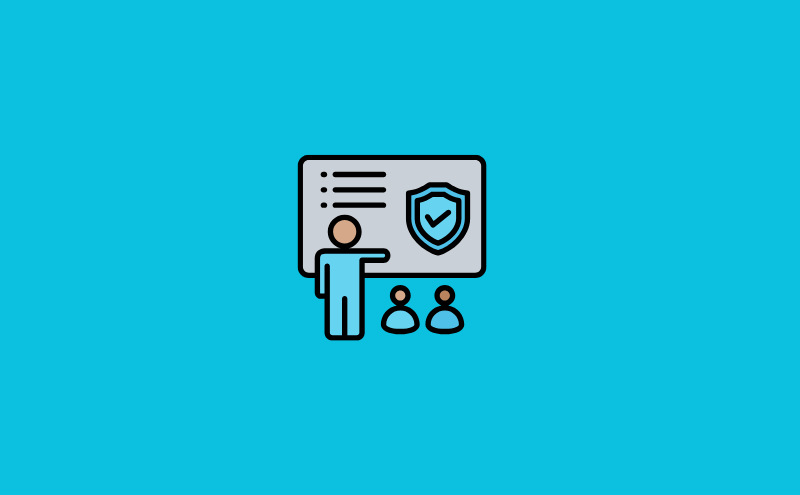
「パスワードの使い回しはダメ!」「怪しいメールは開かないで!」「社外秘の資料は持ち出さないように!」
こんな注意を何度伝えても、社員の行動が変わらない…と感じていませんか?
特に中小企業では、「うちに限って大丈夫」「セキュリティは専門家の話」と思いがちですが、実際に情報漏えい事件は”思わぬ小さな油断”から起こっています。
この記事では、 ITの専門知識がなくても今日から実践できる社内セキュリティ教育のポイントと、実際の進め方を事例つきでやさしく解説します。
なぜ今「社内セキュリティ教育」が必要なのか?データで見る現状
ここ数年、全国の中小企業でも「情報漏えい」や「不正アクセス」などの被害が増えています。大企業だけが狙われる時代は終わり、 “対策が甘い会社ほど被害にあいやすい”ことが分かってきました。
警察庁の調査によると、2024年のランサムウェア被害報告件数のうち、中小企業が半数以上を占めています。また、調査・復旧費用が1,000万円以上かかった企業が約5割、復旧期間は1週間以上かかるケースが約53パーセントに上ります。
小田原・箱根地区でも他人事ではない
神奈川県内でも、実際に以下のような事例が報告されています。
- 退職者のアカウントを削除し忘れ、社内システムに不正アクセスされた
- メールの添付ミスで顧客情報が漏えいした
なぜなら、攻撃する側は「たくさんの会社に手当たり次第に攻撃」しているため、「たまたまパスワードが弱かった」「たまたまウイルスメールを開いてしまった」だけで、誰でも被害者になってしまうからです。
こうした事件は「知識不足」ではなく、 “油断”や”忙しさからのうっかり”が原因になることがほとんどです。つまり、「社員が自分ごととしてセキュリティを考える」ことができていれば、ほとんどの事故は未然に防げるのです。
中小企業が狙われやすい理由
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の報告によると、中小企業がサイバー攻撃の標的になりやすい理由として、以下の点が挙げられています。
- セキュリティ対策の専任担当者がいない
- 限られた予算でIT投資を行う必要がある
つまり、中小企業こそ、基本的なセキュリティ対策を確実に実施し、社員教育を徹底することが重要なのです。
【基礎知識】ランサムウェアって何?知っておくべき最新の脅威
最近ニュースでよく耳にする「ランサムウェア」。これは、 パソコンの中のデータを人質に取り、お金を要求してくるウイルスのことです。「ランサム(Ransom=身代金)」という言葉が由来になっています。
ランサムウェアに感染するとどうなる?
感染すると、以下のような被害が発生します。
- パソコンに保存されているすべてのファイル(顧客リスト、見積書、契約書など)が開けなくなる
- 画面に「データを元に戻したければ○○万円払え」というメッセージが表示される
- 業務が完全にストップし、取引先にも迷惑がかかる
ランサムウェアを防ぐ基本対策
難しい技術は不要です。以下の基本を守るだけで、多くの被害を防げます。
- 重要なデータは必ず「バックアップ」を取る(外付けハードディスクやクラウド)
- 怪しいメールの添付ファイルは絶対に開かない
- パソコンやソフトの「更新(アップデート)」を必ず実行する
これらの対策については、この記事の後半で詳しく解説します。
どこから始める?セキュリティ教育の基礎知識
「セキュリティ教育」と聞くと難しそうですが、まずは「会社の大切なものは何か」をみんなで考えるところから始めましょう。たとえば、以下のものが会社の「守るべき資産」です。
業種別:守るべき重要な資産
旅館・ホテル・宿泊業
- 予約システムのデータ(宿泊予約、顧客履歴)
- 顧客の個人情報(氏名、住所、電話番号)
製造業・町工場
- 設計図面・CADデータ
- 取引先との契約書や見積書
飲食店・土産物店
- POSレジの売上データ
- 顧客台帳(常連客リスト)
士業(税理士・社労士・行政書士など)
- 顧客の財務データ・給与データ
- マイナンバーを含む個人情報
これらが外部に流出したり、勝手に持ち出されたり、ウイルス感染したりすると、取引停止や信用失墜、場合によっては 損害賠償や法的責任につながることもあります。
まず大切なのは「全員が”会社の資産”を正しく理解する」ことです。難しいIT用語ではなく、「大切なもの」「外に出てはいけないもの」を共有するだけで、意識が変わります。
現場でよくある”うっかりミス”とその対策
社内教育の現場でよくある”あるある”をご紹介します。「わかっていたはずなのに、つい…」というミスは、どの会社でも起きがちです。
小田原・箱根地区でよくある業種別”うっかりミス”
旅館・ホテル・宿泊業でのミス
- 予約システムのパスワードを複数スタッフで共有している
- Wi-Fi設定を開業時のまま変更していない
製造業・町工場でのミス
- 図面データをUSBメモリで持ち帰り、自宅で作業
- 退職した従業員のアカウントが残ったまま
飲食店・土産物店でのミス
- POSレジのパスワードが初期設定のまま
- アルバイトスタッフの私用スマホで業務連絡
士業(税理士・社労士など)でのミス
- カフェや電車内で顧客の財務資料を開いている
- マイナンバーを含むファイルをパスワードなしで保存
共通する”うっかりミス”
- 同じパスワードを色々なサービスで使い回す
- 仕事が終わったパソコンをそのまま放置(ログアウトしない)
- 退職者のアカウントやメールアドレスを消さずに放置
こうしたミスは、本人が「悪気がない」「面倒だから後回し」「忙しくてつい」など、気の緩みから起きることがほとんどです。では、どうすればこれを防げるのでしょうか?
自分ごと化できる教育を
人は「自分に関係ない」と思うと注意が向きません。「このミスで会社が困る」「自分がやってしまったら、お客様に迷惑がかかる」という 「自分ごと化」が大切です。
たとえば、実際に過去に起きたミスや、他社の事例をやさしく紹介し、「私たちも気を付けよう」と声をかけると、受け止め方が変わります。
今日からできる!やさしい社内セキュリティ教育の進め方
ここからは、難しい研修や専門用語を使わず、現場で続けやすい教育のやり方をご紹介します。
小さな声かけの習慣から始める
大がかりな研修は必要ありません。まずは日常の中での「ひと声」から始めましょう。
- 「今日もパスワードの使い回し、していませんか?」
- 「怪しいメールは、まず一度相談してOKです」
- 「退職者のアカウント、忘れずにチェックしましょう」
一方的に「やれ」と言うのではなく、 「困ったらすぐ相談していい」「間違いは誰でもある」という雰囲気を作ると、社員も気軽に相談しやすくなります。
1回だけで終わらせないコツ
「今年は研修をやったから大丈夫!」と1回の実施だけで終わると、効果は長続きしません。毎月1回でも、掲示板や社内チャットで「今日はセキュリティの日」「先月はこういうトラブルがありました」と声かけするだけでも、自然と注意が習慣になります。
現場で使いやすい事例・小話を活用
難しい資料より、実際にあった困った話やヒヤッとした体験を共有すると、社員にとって身近に感じられます。
社内で共有しやすい事例
- 「箱根の旅館で、パスワードをメモした紙をなくして大騒ぎになった」
- 「税理士事務所で、カフェのWi-Fiを使って顧客情報を見ていたら、隣の人に覗かれていた」
こうした「他人事ではない」話題を使うことで、社員が「明日は我が身」と感じやすくなります。
【ペルソナ別】実践しやすいセキュリティ対策
ここからは、立場や役割別に、具体的で実践しやすい対策をご紹介します。
経営者の方へ:まず押さえるべき3つのポイント
「ITは苦手だけど、最低限の対策はしたい」という経営者の方に、優先順位の高い対策をお伝えします。
1. バックアップ体制の構築(月額3,000円から)
ランサムウェアに感染しても、バックアップがあれば復旧できます。クラウドストレージを活用すれば、低コストで自動バックアップが可能です。
2. 退職者アカウントの即時削除ルール(無料)
「辞めた人のアカウントが残っていた」という事例が非常に多いです。退職日当日に、すべてのシステムからアカウントを削除するルールを作りましょう。
3. 月1回の「セキュリティの日」設定(無料)
毎月1日など、決まった日に全員でパソコンの更新状況や不審なメールをチェックする習慣を作りましょう。
セキュリティ投資の重要性をお客様にお伝えする際のポイント
テクノリレーションズでは、お客様企業の経営層にセキュリティ対策の必要性をご説明する際、以下のようなお話をさせていただいております。
投資対効果(ROI)の考え方
ランサムウェア被害に遭った場合の平均復旧費用は1,000万円以上、復旧期間は1週間以上です。一方、基本的なセキュリティ対策(バックアップ・セキュリティソフト・社員教育)にかかる費用は年間30万円程度。
つまり、 年間売上の0.1から0.2パーセント程度の投資で、1,000万円以上の損失リスクを回避できます。また、顧客や取引先からの信頼維持という無形の価値も大きなメリットです。
士業(税理士・社労士など)の方へ:顧客情報を守る3つの鉄則
士業の方は、顧客の重要な個人情報や財務データを扱うため、特に慎重な管理が求められます。
-
クラウドサービスは「法人向け・セキュリティ認証取得済み」を選ぶ
無料のクラウドサービスは便利ですが、セキュリティ面でリスクがあります。ISMSやプライバシーマークを取得しているサービスを選びましょう。
-
「外で仕事」をするときのルール作り
- 公共Wi-Fiは使わない(スマホのテザリングを使う)
- 画面に覗き見防止フィルムを貼る
-
顧客への「セキュリティ対策の見える化」
「顧客情報は暗号化したクラウドで管理しています」「プライバシーマーク取得事務所です」とホームページに明記することで、差別化にもつながります。
社員全員が自分ごと化できる教育の”仕組み”を作る
役割分担でみんなが主役
教育は「IT担当」や「社長」だけの役目ではありません。現場のリーダーや若手も交えて、「今月は〇〇さんが注意喚起担当」など役割を回すと、社員全員が当事者として関わるきっかけになります。
できたことを見える化する
「できなかったこと」ばかり責めるのではなく、「今月は退職者アカウントの削除がしっかりできた」「全員がパスワードを変更できた」など、できたことをみんなで共有しましょう。褒め合う文化が、自然と”やる気”につながります。
相談しやすい雰囲気作り
セキュリティの話は、つい「怒られそう」「難しい」と思われがちです。 「分からないことはすぐ聞いてOK」「小さなことでも共有しよう」という空気を作ることが大切です。
外部サポートをうまく使うという選択肢
どれだけルールを整えても、現場では「うっかり」「なんとなく」でトラブルが発生することがあります。これを完全にゼロにすることは困難です。
だからこそ、信頼できる外部パートナーを味方につけておくことが重要です。特に 「IT担当者がいない」「社内に詳しい人がいない」中小企業では、外部の専門家と連携することで安心感が大きく変わります。
こんな場合は専門家への相談を検討してください
- 従業員数が10名以上で、統一的なセキュリティ対策が必要
- 顧客の機密情報を多く扱う業種(士業、旅館、医療など)
- 取引先からセキュリティ対策の証明を求められている
まとめ
社内セキュリティ教育は、「難しい」「面倒」と思われがちですが、毎月の声かけや小さな事例共有だけでも、事故のリスクは大きく下げられます。
小田原・箱根地区には、旅館・製造業・士業など、それぞれの業種特有の課題がありますが、基本的な「パスワード管理」「メール注意」「アカウント削除」「バックアップ」は業種を問わず重要です。
株式会社テクノリレーションズでは、小田原・箱根地区の中小企業向けに、やさしい社内セキュリティ教育のサポートを行っています。「どこから始めればいいか分からない」という方も、 株式会社テクノリレーションズまでお気軽にご相談ください。