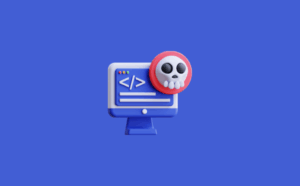やって満足で終わらせない!中小企業のための「情報整理の本当の活かし方」~KJ法からIT活用まで~

「KJ法やマインドマップ、やったことはあるけど、結局その後どうなったんだっけ…?」
情報整理は「やること自体」に満足して終わってしまう会社が少なくありません。しかし本当に大事なのは、その整理した情報が現場で役立ち、業務改善や課題解決につながることです。
この記事では、KJ法をはじめとしたさまざまな情報整理の方法と、よくある“やっただけで終わる”失敗パターン、そして「どうすれば情報整理を会社の力に変えられるのか?」を、IT活用を交えてやさしく解説します。
情報整理は“やったら終わり”でいいのか?
「とりあえず付箋を使ってKJ法をやってみた」「会議でブレインストーミングをしてホワイトボードにまとめた」──こうした取り組みは、業務改善やアイデア出しのきっかけとしてとても有効です。
しかし、現場でよくあるのが「整理して満足」「その後、誰も見返さない」「何も変わらない」というパターンです。本来のゴールは“整理”そのものではなく、業務や働き方をよくすること。情報整理は“手段”であり、目的ではありません。
この章では、なぜ情報整理が「やったら終わり」になってしまうのか、背景を探っていきます。
情報整理の“手法”はいろいろある
情報整理にはKJ法だけでなく、いろいろな方法があります。それぞれ特徴や向いているシーンが違いますので、自社の現場に合うものを選ぶことが大切です。
KJ法(付箋でグルーピング)
メンバー全員が自由に意見やアイデアを書き出し、似ているもの同士をグループ化してまとめていく方法です。「頭の中が整理される」「抜け漏れが見つかりやすい」というメリットがあります。
マインドマップ(頭の中を見える化)
中心にテーマを書き、そこから連想するキーワードやアイデアを枝分かれの形で広げていく方法です。「アイデアの広がりを視覚的に把握しやすい」「一人でも短時間でできる」などの特徴があります。
ロジックツリー(課題を深堀り)
大きな問題や課題を「なぜ?」「どうして?」と枝分かれで細かく分解していく方法です。「本当の原因を深掘りしたいとき」に効果的です。
タイムライン法(時系列で整理)
起こったことやアイデアを時系列に並べて整理する方法です。プロジェクトの進捗や業務改善の変化を見える化したい時におすすめです。
SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)
会社やチームの「強み・弱み・チャンス・リスク」を4つのカテゴリーで整理し、現状把握や戦略づくりに活用する方法です。
ブレインストーミング(アイデア出し+分類)
複数人で自由にアイデアを出し合い、その場でどんどん書き出していく手法です。出たアイデアを後からグループ分けしたり、優先順位をつけていくことで情報整理につなげます。
このように多彩な方法がある一方で、大切なのは「自社の目的や規模、実情に合った手法を選ぶ」こと。やり方だけにこだわる必要はありません。
なぜ“やって満足”で終わってしまうのか
「せっかく整理したのに、誰も見返さない」「1回やったきりで放置」「担当者がいなくなったらそのまま」──こうした事例は多くの会社で起きています。その理由を挙げてみます。
- 情報の置き場所やフォーマットがバラバラで、後から探しにくい
- そもそも“なぜやるのか”が共有されていない(やらされ感)
- 整理だけで満足してアクション(改善策)までたどり着かない
- 誰が管理・更新するかがあいまいで、結局“放置”される
- 会議やワークショップの場限りで、その後につながらない
「やっただけで終わる」のは、目的や活用イメージが共有されていないからというのが大きな原因です。
“コンサルに言われたから”やっただけ…納得感ゼロの悲劇
中小企業の現場で多いのが、「コンサルタントに勧められたから」「補助金申請のために必要だと言われたから」情報整理を導入したものの、意味も分からず形だけやったケースです。
最初はコンサルタントがリードしてうまく進んだように見えても、しばらくすると担当者もコンサルもいなくなり、「誰も運用できず、古い資料だけが残る」「何をやったのか分からない」…ということに。
こうならないためには、
- 自社の経営層・現場が「何のためにやるか」を納得している
- 社内で続けられる仕組み・ルールを作る
- もし外部の支援を受ける場合でも“自分ごと化”しておく
といった工夫が欠かせません。
情報整理の本来のゴールは“業務改善・課題解決”
「情報を整理すること」はあくまで手段であり、本当のゴールは“課題を見つけ、改善アクションにつなげる”ことです。
例えば、KJ法で現場の困りごとを集めたら、次は「この課題をどうやって解決する?」まで一歩踏み込みます。整理した内容をもとに、改善策を決め、担当と期限もセットで決めておくと、実際にアクションにつなげやすくなります。
また、改善した内容は「振り返り」や「定期的な見直し」を必ず行いましょう。PDCA(計画・実行・確認・改善)サイクルを意識すると、整理した情報が会社の“資産”として活きてきます。
“行動につなげる”情報整理の工夫
情報整理の価値は、実際の業務や日常の行動に落とし込んでこそ発揮されます。具体的な工夫を紹介します。
- 整理した内容をタスク管理表やToDoリストにまとめ、担当・期限を明確にする
- 会議や朝礼、定例会で「前回のまとめ」を必ず見返し、進捗確認の習慣にする
- チャットや掲示板など“みんなが見る場所”に情報を固定表示
- 「改善アクション」は小さなことから始めて、必ずフィードバックの場を設ける
このように、“見える化”から“行動化”へ落とし込むことが、形だけで終わらせない最大のポイントです。
ITを使ってラク&確実に続ける
「整理した情報を活かす」「継続的に見返す」「みんなで共有する」──この3つを実現するには、ITの活用がとても効果的です。
- GoogleドライブやOneDriveなどクラウドストレージで「どこからでも」「誰でも」アクセスできる仕組みを作る
- NotionやEvernote、社内Wikiなどで“ナレッジの見える化・簡単更新”を実現する
- タスク管理ツール(例:Trello、Asanaなど)で改善アクションを割り振り、進捗を可視化する
- 社内チャットや掲示板で日々の共有・振り返りを簡単に行う
ただし、最初から全部IT化する必要はありません。「まずは1つの会議議事録をクラウドに置くだけ」「改善アイデアをスマホで撮ってチャットに投稿するだけ」など、小さく始めるのがおすすめです。
続けるための“ちょっとしたコツ”
どんな仕組みも「続かなければ意味がない」──これが現場で一番大切なポイントです。無理なく続けるためのヒントをまとめました。
- 最小限から始めて、慣れてきたら徐々に拡大(いきなり全部デジタル化しない)
- “誰がやるか”を必ず決める(情報管理担当やITサポーターを設置)
- 月1回など“見返しの習慣”をチームで作る
- 「困ったら誰に相談できるか」を明確にしておく
- 外部のITサポートやコンサルを活用する場合も、「運用ルール」や「役割分担」を最初に決めておく
“続ける仕組み”があることで、情報整理の価値が何倍にもなります。
情報整理の“失敗あるある”と学び
最後に、よくある失敗例と、そこから学べる教訓を紹介します。
- 付箋やノートが山積みで、誰も見返さない(置き場所・フォーマット統一の重要性)
- 「担当者がいない」「忙しくて続かない」(役割の明確化・簡単な仕組み化)
- ITツールを入れたものの、誰も使いこなせなかった(無理なIT化は逆効果。シンプルに始める)
- コンサルに頼りきりで、社内にノウハウが残らない(“自分ごと化”と社内メンバーの巻き込みが必須)
失敗から学び、次は“小さく始めて、みんなで続ける”工夫が大事です。
まとめ:やったら終わりにしない情報整理で、“活きる会社”に
情報整理は手段であって、ゴールではありません。大切なのは「整理した情報を、現場のアクションや改善につなげること」。
そのためには、目的やメリットの共有、行動への落とし込み、そして無理のないIT活用が欠かせません。
「とりあえずやって終わり…」を卒業し、“情報を会社の力に変える仕組み”をぜひ作ってみてください。
株式会社テクノリレーションズでは、中小企業の実情に合わせた情報整理・IT導入・定着支援をワンストップでご提供しています。
「情報整理が続かない…」「ITをうまく活用したい」というお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
ITのお困りごと、まずはお気軽にご相談ください
小田原・箱根・西湘エリアに密着。中小企業の「困った」を、電話一本で解決します。